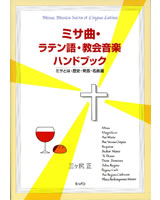
ミサ曲・ラテン語・教会音楽ハンドブック
ミサとは・歴史・発音・名曲選
三ヶ尻 正 著
■B5判/216ページ
■定価:本体2,000円+税
■ISBN 978-4-88364-147-5
「ミサ曲」を歌う演奏家やアマチュアの方のため、理解が深まり、よりレベルの高い「ミサ曲」が歌える事を目標に、コンパクトにわかりやすくまとめました。
もくじ
はじめに
第1部 「ミサ」と「ミサ曲」
第1章 「ミサ」とは
第2章 「ミサ」のかたち
第3章 「ミサ曲」とその歴史
第2部 「ミサ曲」とラテン語
第4章 「ミサ曲」とラテン語
第5章 「ミサ曲」の発音・ディクション
第3部 ミサ曲以外のラテン語教会音楽
第6章 ミサ曲以外のラテン語の教会音楽
参考文献
あとがき
はじめに
日本は合唱の盛んな国です。年末にはベートーヴェンの「第九」が各地で歌われますし、ハレルヤ・コーラスで有名なヘンデルのオラトリオ「メサイア」も定番になっています。こうした合唱曲のレパートリーの中で大きな位置を占めているのが「ミサ曲」です。「第九」や「メサイア」のように、同じ曲を同じ団体が毎年歌うような例はあまり聞きませんが、それでも大きな合唱団では、ある年はベートーヴェンの「荘厳ミサ曲」をある年はモーツァルトの「戴冠ミサ曲」を、またある年はバッハの「ロ短調ミサ曲」を歌う、という風に多数の「ミサ曲」を取り上げているところもあります。個々の曲の演奏回数では到底およばないとしても、「ミサ曲」としてまとめれば、ひょっとすると「第九」や「メサイア」と肩を並べるほどの演奏回数かもしれません。
ミサ曲のほとんどは「ミサ通常文」(本文13ページ参照)で書かれています。同じテキストなので、どれか一曲歌っておけば、他の曲を歌うときも歌詞を読んだり覚えたりする手間が省けます。発音もローマ字的なので、英語やフランス語、ロシア語のような苦労もありません。
ところで、この「ローマ時的」というところがクセモノです。たとえば「グローリア」に"Gratias Agimus Tibi"という一節がありますが、[グらーツィアス]なのか[グらーティアス]なのか迷ったことはありませんか? [アヂムス]でしょうか、[アギムス]でしょうか? 「クレド」に"sub Pontio Piato"とありますが[ポンツィオ]でしょうか、[ポンティオ]でしょうか? "Homo"は[オモ]でしょうか、それとも[ホモ]でしょうか?
これらは、大きく分けてイタリア式発音・ドイツ語式発音・古典式発音の3つの流派に大別できますが(ほかに、イタリア式の中の教会式、フランス式、スペイン式、中世フランドル式など、各地各時代の方式があります)、どれが正しいというのではなく、地域と時代、作曲の背景、そして演奏者の解釈などによって差の出てくる問題です。
本書では、古今の「ミサ曲」を歌う皆さんのために、ミサとは何か、ミサとミサ曲の歴史、ラテン語の発音など「ミサ曲」にまつわるさまざまな事柄を解説して行きます。演奏家にとって大きな関心事である「発音」に多くを割きましたが、背景となる歴史やキリスト教の教義にも触れておきました。きっと作品理解の上でも役立つものと思います。
さらにミサ曲以外のラテン語の教会音楽についても、簡単ではありますが代表的な曲の概要と発音を解説してあります。
歌の練習により多くの時間を割きたい演奏家や、なかなか歌う時間を工面するのが大変なアマチュアの方々のことを考え、内容はできるだけコンパクトに分かりやすくまとめたつもりです。「ミサ曲」やラテン語について、より詳しくは、先人のすぐれた著述がいくつもありますので、巻末の参考文献リストなどを参考に読み広げていただければ、と思います。
なお、お断りしておかなければなりませんが、著者はキリスト教信者ではありません。信仰の立場とは違う見方だったり、理解が浅い、あるいは誤っている場合もあるかもしれませんが、教会の外から見ているという立場をご理解の上で読んでいただければ幸いです。
本書を通じて、日本で「ミサ曲」を歌う方々の理解が深まり、よりレベルの高い「ミサ曲」の演奏が増えることを願ってやみません。
2001年6月 著者
ご注文や在庫の有無、送料の確認など、お問い合わせは、ハンナ営業部
電話:042-506-1353 / FAX:042-506-1354
または下のメニューのお問い合わせフォームよりどうぞ。
なお、お近くの書店や楽器店でのお取寄せも受け付けております。


