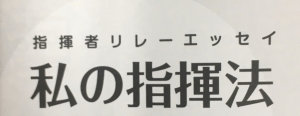続・うたの魅力 うたの魔力
――飯守泰次郎インタビュー(後編)
これまでにさまざまな“うた”を振り、指揮者として“うた”を極めてきた飯守泰次郎氏。
前回に引き続き、うたの魅力を語っていただいたが、今回のメインテーマは“オペラにおける合唱”。
氏の考える、オペラの劇中にある合唱とはなんなのか。
聞き手:四野見和敏(指揮者)
(こちらの記事はうたの雑誌「ハンナ」2013年7月号掲載記事です)
――今回はオペラにおける合唱の魅力についてお話ししていただきたいと思います。今年はヴェルディとワーグナーの生誕200年にあたる年なので、両作品のなかで合唱はどんな役割を持っているかを探ってみたいと思います。オペラの中で合唱団は一般庶民から身分の高い人々、さまざまな社会階層の人々として登場しますね。ヴェルディの作品において合唱の役割と音楽的な特徴をあげていただけますか。
ヴェルディのオペラにおける合唱では、現実の社会または歴史の中で生きた実在の人々が、リアルに描かれていることが多いと思います。
例えば『椿姫』の中で合唱を歌う人々は、1850年代に実際にパリの社交界で生きた紳士淑女です。有名な「乾杯の歌」は、杯を交わしながら生の喜びや快楽を歌い上げる、まばゆいばかりの合唱です。
『アイーダ』の「凱旋の行進」の場面で登場する合唱は、エジプトの民衆や聖職者です。民衆が勝利に沸き立つ歓喜の合唱と、神々に感謝する僧侶たちの力強い合唱で構成されています。この合唱は非常に劇的かつ大規模であり、ワーグナー的ともいえるほどで、やはり二人が同じ時代を生きていたことが実感されます。『アイーダ』という大スペクタクルを壮大なスケールで描くには、このような合唱こそが一番適した表現手段だったのです。
一方『ナブッコ』では、バビロニアに敗れたヘブライ人たちが故国への思いを歌います。『アイーダ』が勝者の合唱であるのに対し、『ナブッコ』のこの合唱は抒情性の溢れたメロディーが非常に美しく、それが特に名曲として人々に愛される理由なのでしょう。
『トロヴァトーレ』に登場する合唱は、兵士や修道女やジプシーたちです。このオペラにおける合唱は、ストーリーの上でも、ソリストとの関係においても、重要な役割を果たします。合唱がソリストの深い心理を映し出したり、ソリストの感情を増幅したりする場面があります。
例えば、兵士たちはフェルランド(警備隊長)の恐ろしい話を興味津々で聞き、興奮したり怒りに燃えたり恐怖におののいたりして、緊張感のある場面を作っています。また、第2幕のルーナ伯爵がレオノーラを連れ去ろうとする場面では、伯爵の邪悪な思惑に家臣たちの合唱が同調したり、あるいはそれを代弁したりします。それに対して、レオノーラを支える修道女たちは、彼女の不安や憧れに合唱で寄り添います。
音楽的なコントラストが見事な場面です。またマンリーコが兵士を引き連れて戦いに行く場面では、兵士の合唱が闘争心をあおります。このように、ヴェルディは、合唱で生身の人間の喜怒哀楽をドラマチックに描くのです。
――次に、ワーグナーでは合唱の持つ意味や、特徴はどんなところにありますか。
合唱で人間の感情を直接的に表現するヴェルディと比べると、ワーグナーの合唱の響きは内面的で、精神性、ロマン性、哲学性、神秘性が感じられます。ワーグナーの『タンホイザー』と『パルジファル』においては、官能性と宗教的な救済という対極的なテーマが中心となっており、合唱もこうしたテーマにふさわしい内面的な表現を担います。
『タンホイザー』における「巡礼の合唱」や『パルジファル』の幕切れの合唱は、舞台の空間性を生かした清純で崇高な響きが、深い宗教性や精神性を表現します。一方で、同じ『パルジファル』の中の「花の乙女たちの合唱」は対照的に、主人公を女性たちが誘惑する官能性に満ちており、ここでは聴き手の感覚や本能を直接的に刺激するような響きも持っています。
またワーグナーは、群衆あるいは民衆の持つ大衆性をエネルギッシュに描くことも得意です。『さまよえるオランダ人』の「水夫の合唱」は、航海を終えて故郷に上陸する水夫たちの解放感が爆発する、陽気で粗野な迫力の溢れる歌です。祝い酒の勢いも手伝って、まるでお祭り騒ぎです。そこに幽霊船から響いてくるデモーニッシュな合唱が重なり、健康的な水夫たちとのコントラストが見事です。『ニュルンベルクのマイスタージンガー』第2幕では、街中を巻き込む激しい喧嘩のシーンで、民衆の興奮が極限状態までリアルに描かれており、音楽的にも大変難しいアンサンブルが要求される部分です。ここは、人間の原始的な性格がむき出しにされる場面です。
『ローエングリン』は、ワーグナーの作品のなかでも特に合唱が多く登場し、ドラマの進行において極めて重要な役割を担います。ギリシャ悲劇の時代には『コロス』という合唱隊がいて、聴き手の理解を助けたり、聴き手の感情を代表したりする役割を持っていましたが、『ローエングリン』における合唱は、このコロスの要素を強く持っています。
ブラバントの人々やザクセン人の軍勢など、それぞれの集団の持つキャラクター(規律、習慣、思考様式、歴史など)も、合唱を通して前面に出てきます。『ローエングリン』の第1幕では、合唱がまさにコロスの役割を持ち、ドラマの進行やソリストの行動を時には先取りしながら、主体的にソリストの歌唱に絡みます。人々の興味や関心が今どこにあるのか、合唱が聴き手に刻々と伝えるのです。
ここでは、合唱団の一人一人が、実在の人間と同様に誇りを持ち、驚き、怒りまた嘆き悲しみ、時には決断することが求められます。あるいは、エルザの婚礼の前の「大聖堂への行列」の場面は、大変繊細な表現が求められる合唱です。集団の中にいる一人一人の心理まで伝わってくるような、大変美しく透明な響きです。特に『ローエングリン』の中の合唱は伝統的なドイツの合唱の響きがあり、それが魅力となっています。
それだけに、ドラマの奥行きを深めるためには、それぞれの場面の言葉が持っている発音的特徴や音色を合唱全体の響きに活かさなければなりません。
――ヴェルディとワーグナーを比較して、合唱表現の特徴に違いがありますか。どこにヴェルディらしさやワーグナーらしさを感じますか。
まず、規模の違いがありますね。両者とも大人数の合唱を使いますが、やはりワーグナーの方がより大規模で、響きも厚いですね。しかし一番本質的な違いは、やはりそれぞれの作品の内容であり、そのために必要とする表現も異なるということです。
イタリアといえば歌の国であり、ラテン系の民族です。ヴェルディのオペラは、生身の人間の生きざまを、ありのままに赤裸々に描きます。誰にでも起こり得る人生の過酷な運命、爆発するような喜びあるいは身を切るような悲しみの感情……全てを歌そのもので表現するのです。したがって、ヴェルディの合唱はメロディー優先であり、それが聴き手の感情にじかにリアルに訴える力につながっていると思います。
美しく力強いメロディー、あるいはイタリア・オペラの伝統である「ベル・カント」(「美しく歌う」の意)の要素は、ヴェルディの合唱曲でもいかんなく発揮されています。さすがイタリアの作曲家だと思います。また、ユニゾン(全員が同じメロディーを歌うこと、斉唱)が多いこともヴェルディの特徴です。メロディーの持つ雄大さ、開放性、抒情性が、ユニゾンの一体感がある響きと共に大きなうねりとなって劇的効果を高めているのです。
一方、ゲルマン系のワーグナーのオペラ・楽劇では、思想、哲学、宗教性、世界観などが表現の前面に出てきます。合唱においても、ハーモニーの発展性が重視され、転調による響きや音色の変化で、ドラマの展開と内面的な表現を支えています。ユニゾンはあまり用いられず、非常にコラール的で重厚なハーモニーが主体で、リズム的な構築性とその発展も重要な要素です。
内面に深く浸透する繊細な響き、重厚な響き、迫力ある響き、崇高で清純な響きなど、さまざまなハーモニーの変化を駆使した効果的な表現がされます。ワーグナーは、ドイツ・ロマン派から受け継いだ作曲技法を限界まで拡大し、調性とハーモニー、リズム、音型とその発展といった論理性によって聴き手の理性に影響を与え、結果として聴衆の心を操作するほどの効果を持つに至ったのです。
同じ年に生まれながら、イタリアのヴェルディとドイツのワーグナーは対照的な存在です。同じヨーロッパでも、南のイタリアと北のドイツでは、これだけ違うのです。それでいて、精神的に強い内容を持った音楽を書いたという点で二人は非常に共通しています。同じ時代を生きただけに似ている面もあり、いっそう違いも際立って感じられるのですね。
――どうもありがとうございました。
(うたの雑誌「ハンナ」2013年7月号より。前編はこちら)
この記事を掲載のハンナ2013年7月号はこちら
この他のハンナの過去掲載記事はこちらから