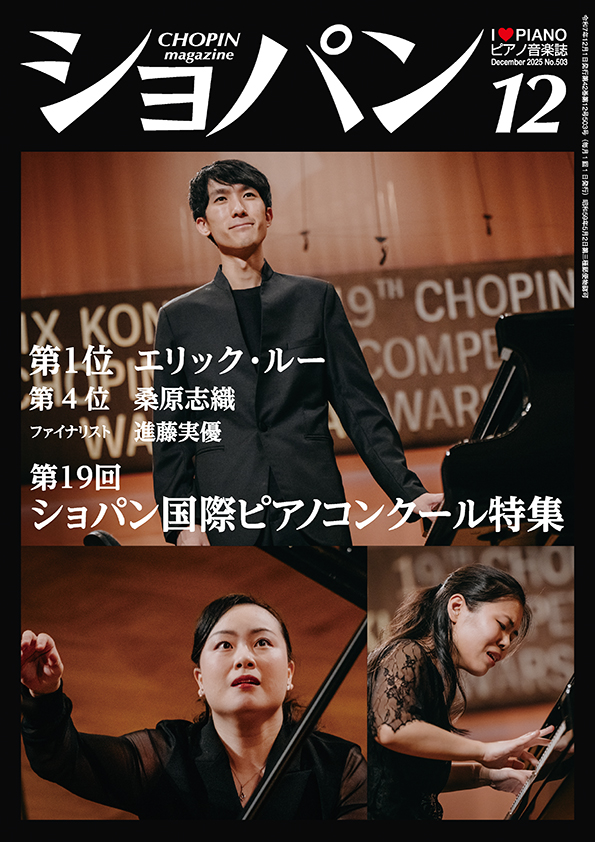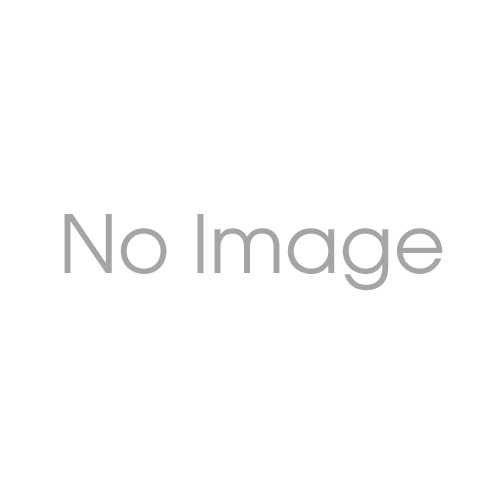
歌うドイツ語ハンドブック 歌唱ドイツ語の発音と名曲選
三ヶ尻正著 から
はじめに
人気の高いドイツ語の声楽曲・合唱曲
クラシックの声楽曲では、イタリア語とドイツ語が二大勢力です。イタリア・オペラはいつも花形で人気の高い分野ですが、その一方でドイツ・オペラやドイツ・リート、それにバッハをはじめとした宗教曲などドイツ語の曲も根強い人気があります。
日本で一番知られているドイツ語の曲といえばベートーヴェンの「第九」でしょう。年末に各地で歌われているので、クラシック・ファンならずとも知っています。「もみの木」や「流浪の民」を合唱で歌った人も多いのではないでしょうか。
リートでは「魔王」や「菩提樹」「ます」を書いたシューベルト、「詩人の恋」「女の愛と生涯」のシューマン、それにヴォルフやマーラー、リヒャルト・シュトラウスなどロマン派を中心に幅広いレパートリーがあります。
ドイツ・オペラも、モーツァルト「魔笛」、ベートーヴェン「フィデリオ」、ウェーバー「魔弾の射手」から、ワーグナーの楽劇、リヒャルト・シュトラウス、アルバン・ベルクの「ヴォツェック」「ルル」、はてはブレヒト(台本)/クルト・ヴァイル(作曲)の「三文オペラ」に至るまで、一大分野を成しています。
宗教曲ではバッハの「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」が筆頭でしょうけれども、バッハにはカンタータやモテット、「クリスマス・オラトリオ」など200曲を越す声楽曲があり、シュッツやテレマンの作品もあれば、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」やブルックナーの詩篇歌もあります。
やさしい(?)発音ε
ドイツ語は、文字から音にするのは比較的やさしい言語といえるでしょう。ローマ字的ですし、そうでないところでもスペルと発音の関係がほぼ一定です。フランス語のように難しい鼻母音やリエゾンで泣かされたり、英語のようにスペルと発音がバラバラということもありません。
しかしその一方で、ウムラウト(ä,ö,ü)やβ(エスツェット)などの見慣れない文字があったり、"ei"を[アぃ]"eu","äu"を[オぃ]と読むなどの特殊なスペルがあったり、あるいは"s+母音"が濁って「ザ行」になるなど、憶えなくてはならないルールもあります。
さらに、歌詞に込められた内容を深く聞かせようという段階になると、一層厳しくなってきます。ドイツ語圏では「リート」という、詩と音楽が密接に結びついた分野が発展したために、歌詞をより明瞭に、より多彩に聞かせることが重要になりました。イタリア語だろうとロシア語だろうと、歌詞のニュアンスまで表現しようとするのに簡単な言語など一つもないのですが、ドイツ語の発音に対する厳格さは群を抜いていると思います。"e"の文字に[e;][ε][(小文字のeの上下逆)]等何種類もの音があることなど、普通の日本人にはこだわり過ぎに思えるかもしれませんが、ドイツ人にとっては重大問題です。
またドイツには「舞台発音」という演劇界・音楽会の伝統的な発音体系・教育体系もあります。
本書の前半、第1部〜第3部(第9章まで)では、こうしたドイツ語のスペルと発音について初心者から上級者までを対象にしたノウハウを綴ってあります。日本人の声楽家・合唱団員にとって難しい発音、見落としがちな発音上の注意点を幅広くカバーしました。ドイツでの舞台発音・歌唱発音の伝統と近年の傾向についても触れてあります。
後半の第4部(第10章)ではソロや合唱の代表的な曲を取り上げ、一曲ごとに歌詞の発音、逐語解説、対訳を付けました。はじめてドイツ語で歌う方なら、リート・オペラ・受難曲のソロを歌う人まで、楽しみながら学んでいただけると思います。
本書の使い方ですが、通読でなく興味あるところだけ拾い読みしていただいても結構です。練習の合間や本番を待つ舞台袖で聞いてみる、といった使い方も歓迎です。発音の中・上級編(第2・3章)や舞台発音(第5章)、語学の話(第3部)など専門的で読みにくければ、斜め読みするか、そのうち読むつもりで飛ばしてもいいでしょう。ただ第4部の名曲選はぜひ皆さんに読んでいただいた上で、歌ったりCDを聞いたりしていただきたいと思っています。
本書がきっかけとなって、ドイツ語の声楽曲・合唱曲がより多く、より深く歌われるようになることにつながれば、著者にとって望外の幸せです。
歌うドイツ語ハンドブック 歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻正

.png)



 (1).png)