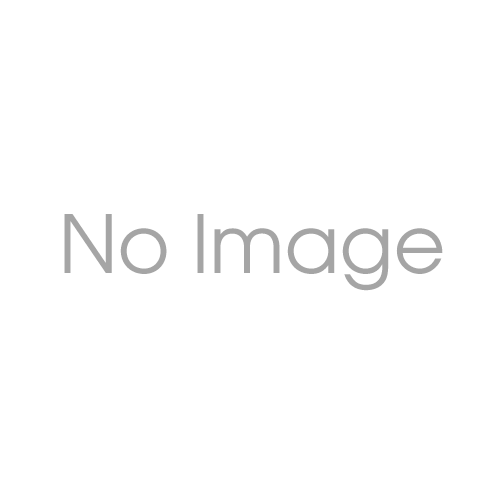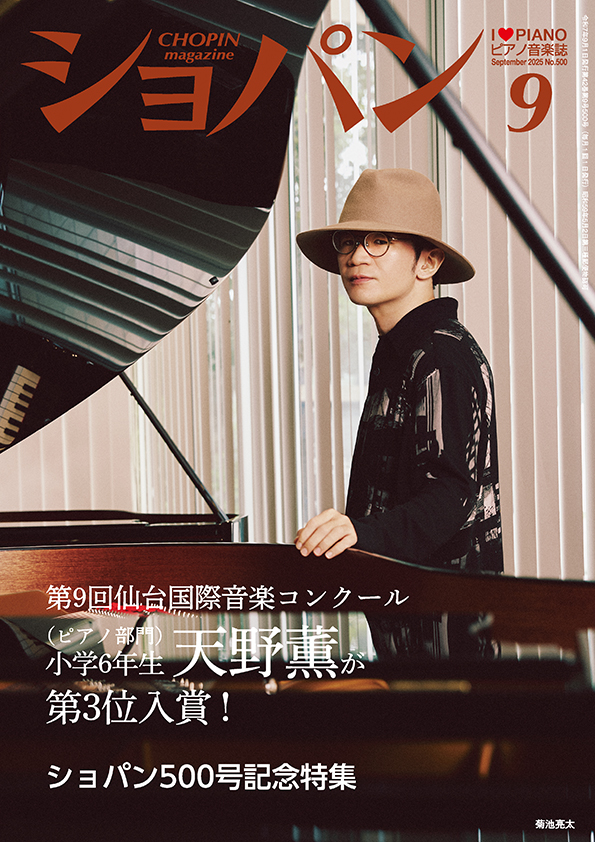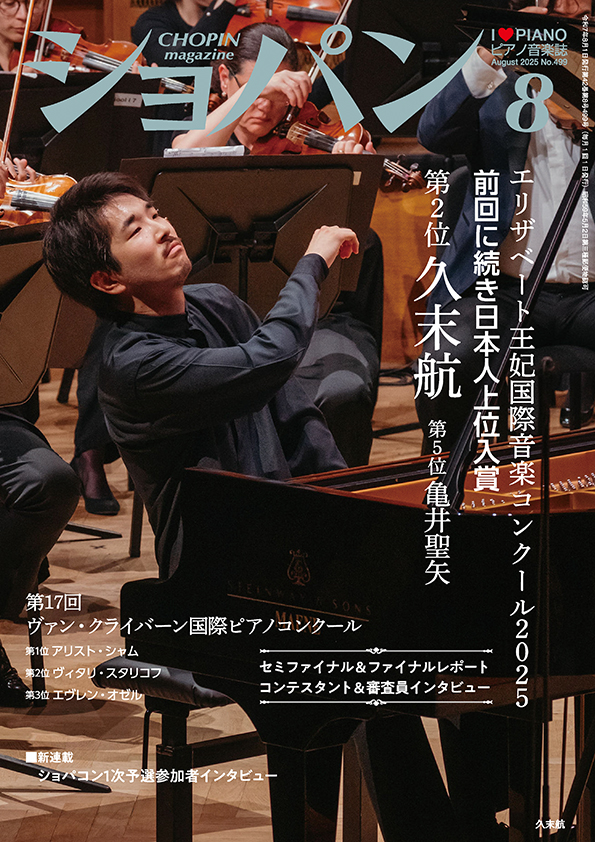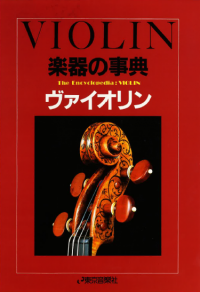
ヴァイオリンの才能教育
1945年の終戦で、日本の大都市のほとんどは焼土と化し、ヨーロッパ諸国のヴァイオリン製造の激減と共に、ヴァイオリンーブームが去り、弦楽器としてはギターがもてはやされる時代が続いたが、この時期のヴァイオリンの生産を支えたのは、鈴木鎮一が1946年に長野県の松本で始めた、ヴァイオリンの才能教育運動であった。1946年といえば終戦の翌年で、鈴木バイオリンにとっても混乱期であった。今では過ぎ去ったことではあるが、川崎の六郷に鈴木バイオリン研究所ができてこれが間もなく国際音楽学校に変ったり、木曽福島の旧グライダーエ場に別の鈴木バイオリンの製作工場ができて、これが分裂して日本弦楽器共同組合が出現したりして、一時的な騒動が持ち上ったと伝えられているが、鈴木鎮一が推進する画期的な才能教育は、わが国のヴァイオリンの隆盛を飛躍的に導き出し、幾多の優れた奏者を生み出すと共に、鈴木バイオリンの名声を世界中に伝播したのである。
なお、現在ではアメリカ、カナダを始めとしてヨーロッパのすみずみの国まで、このヴァイオリンの才能教育を、わが国で聞く以上に、賞讃している。
(注)、木曽鈴木バイオリンは、1983年に倒産。その翌年である1984年に現在の木曽バイオリンが誕生している。
戦前の鈴木バイオリンの殆どはブルーサイズつまり4/4のものであったが、才能教育の普及によって、分数ヴァイオリンの需要が急増した。
わが国の分数ヴァイオリンには3/4、1/2、1/4、1/8、1/10、―/16の六種類があるが、ヨーロッパの楽器では、レディーサイズとよばれる、4/4より少し小さい7/8という特殊な楽器はあるが、分数ヴァイオリンとしては3/4、1/2、1/4だけで、その数も極めて少なく、そのサイズも、わが国のものとは一致せず、統一されていない。
1950年代には、日本のヴァイオリン属の楽器のメーカーとして、次に列挙する数多くのものがあった。
☆猪子宕祐(徳島市)
☆日本バイオリン研究所(長野県上伊那郡飯島町)
☆日本弦楽器企業組合(長野県西筑摩郡福島町)
☆日本工音有限会社(長野県諏訪市)
☆東京工業大学永廻研究所(東京都目黒区大岡山)
☆茶木泰寛(東京都文京区)
☆金子二郎(兵庫県尼ヶ崎市)
☆吉田楽器製作所(名古屋市東区筒井町)
☆タスカ楽器製作所(愛知県春日井市)
☆ツノダバイオリン楽器製作所(東京都荒川区日暮里町)
☆前田バイオリン製作所(名古屋市千種区ふ松町)
☆寺田楽器製作所(名古屋市東区小川町)
☆佐藤楽器製作所(名古屋市東区筒井町)
☆木下弦楽器研究所(東京都渋谷区代々木)
☆響盟社(長野県伊那市)
☆水野楽器製作所(名古屋市千種区千種通)
☆菅沼源太郎(東京都世田谷区新町)
☆鈴木バイオリン社(長野県西筑摩郡福島町)
☆スズキシロー・バイオリン研究所(長野県松本市)
☆鈴木バイオリン製造株式会社(名古屋市中川区広川町)
☆恵那弦楽器製作所(岐阜県恵那市)
☆大塚洋楽器製作所(東京都北区田端新町)
しかし、残念なことに、現在ではこれらのメーカーの一部を除いては殆ど消滅してしまい、楽器も残されておらず、資料すら探し出すことが困難である。
(注)、イタリアのすべてのマスター・ヴァイオリンのメーカーのリストの明細は、付録で記載した通り、専門書として残されている。わが国では、企業としての利潤を追求する余り、文化的な遺産も貴重な資料も顧みられない傾向がある。
その当時の宮本金八氏および峯沢宮藏氏などの手工品の楽器には驚くほどの優れたものがあった。
楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第1章 45 各国のヴァイオリン
▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次