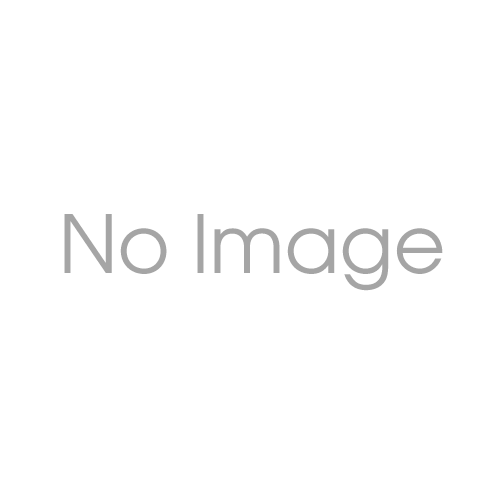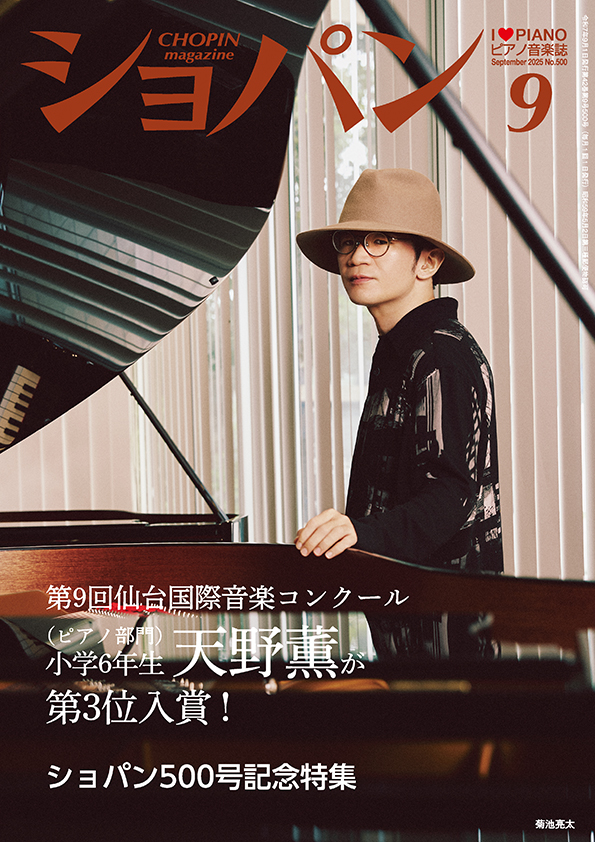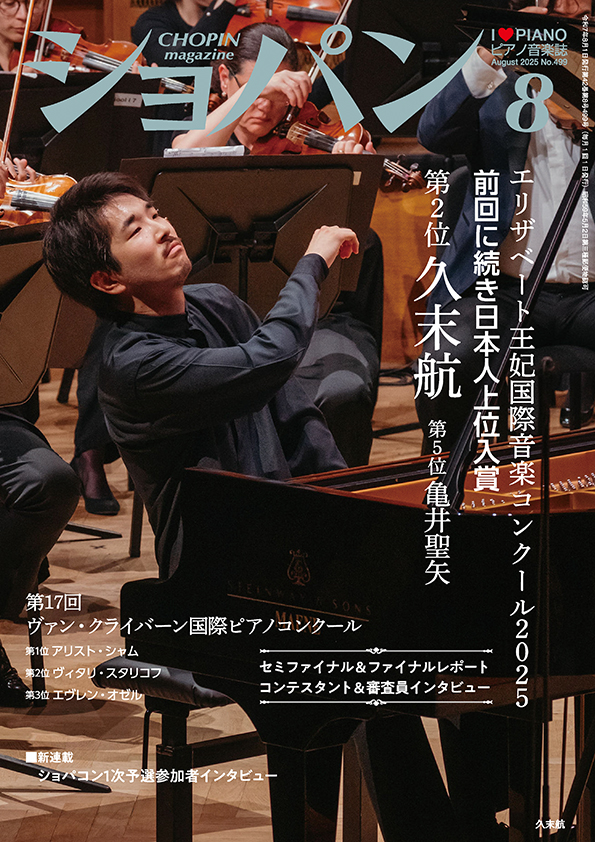[画像]ブーベンロイト弦楽器博物館
第二次世界大戦
しかし、問題は第二次世界大戦であった。ヨーロッパ諸国も日本も戦禍で荒廃し、ヴァイオリンの生産が回復するには十年以上も掛ったのである。第二次世界大戦では、一時期世界の量産ヴァイオリンの主導権を握っていた、フランスのミルクールが再度にわたって大打撃を受けたのは云うまでもなく、ドイツのマルクノイキルヘンのヴァイオリン産業も苦境に立つこととなった。
ドイツは、連合軍の占領下にある自由主義の西ドイツと社会主義の束ドイツに分割され、マルクノイキルヘンのヴァイオリン・メーカーの一部は、社会主義を嫌って、西ドイツのエルラングン近郊のブーベンロイトに移住し、新しいヴァイオリンの町を作り上げた。
さらに、チェコスロヴァキアのシェーンバッハ(チェコ語の名称はルビー)の大部分のメーカーたちも、国境を越えてブーベンロイトに逃げ込んだ。
当時のブーベンロイトは人口300人程度の寒村であったが、忽ち3000人の人口に膨れ上り、第二次世界大戦後のヨーロッパの大量生産のヴァイオリンと弓を支えたのである。
現在、ヴァイオリン・メーカーが約25社、弓のメーカーが約20社あるといわれているが、その90%はチェコスロヴァキアからの移民であると伝えられている。
このような状態が起ったため、第二次世界大戦以前の繁栄を続けていた東ドイツのマルクノイキルヘンとチェコスロヴァキアのシェーンバッハはもぬけの殼のような状態となり、西ドイツのブーベンロイトは急激に繁栄し、現在もその状態を続けている。
その理由は、自由主義経済と社会主義経済との組織の相違にあった。
ブーベンロイトの楽器は、自由経済の原則に基いて、素早く世界中に販売されたが、マルクノイキルヘンおよびシェーンバッハのヴァイオリンや弓は、東ドイツのデムッサ公団あるいはチェコスロヴァキアのリグナ公団(後のアマティ公団)の制約を受けて、価格も統制され、その販売の交渉が一方的でしかも極めてスローであったためである。
第二次世界大戦で、ヨーロッパ諸国における数多くのオールドーヴァイオリッが失われ、さらに戦火から逃れた楽器も国外へ持ち出された。最も安泰であったのはアメリカに集められていた数多くの名器であった。
なお、多くのマスター・ヴァイオリンのメーカーたちは故国を捨ててアメリカなどに移住し、さらに、手工ヴァイオリンの本場であるイタリアでは、メーカーたちが増え、各地で玉石混淆のさまざまな楽器を作り始め、それらの大部分はアメリカに輸出されていた。
この頃から、オールドーヴァイオリンの値段は、戦後のインフレーションをはるかに上回るほどの高価なものとなり、19世紀および20世紀の半ば頃までに作られた、セミ・オールドともよばれるイタリアのマスター・ヴァイオリンの需要も急速に拡大していった。
世界の大都市のヴァイオリン商は、殆ど戦争の影響を受けることなく、ストックとして持っていたこれらの楽器で思い掛けない利益を得たのである。
 [画像]エッカード・ザイドル (マルクノヘイキン) のマスターヴァイオリン
[画像]エッカード・ザイドル (マルクノヘイキン) のマスターヴァイオリン
楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第1章 43 日本のヴァイオリン
▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次