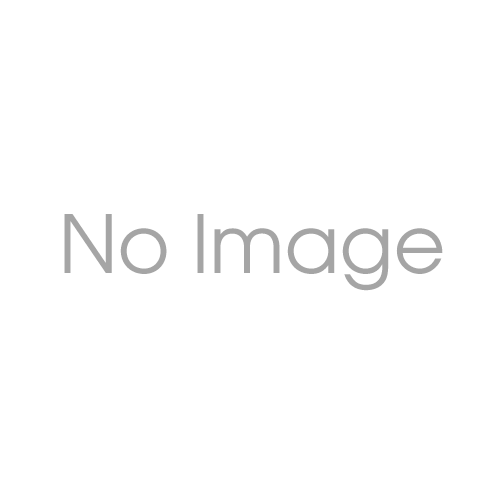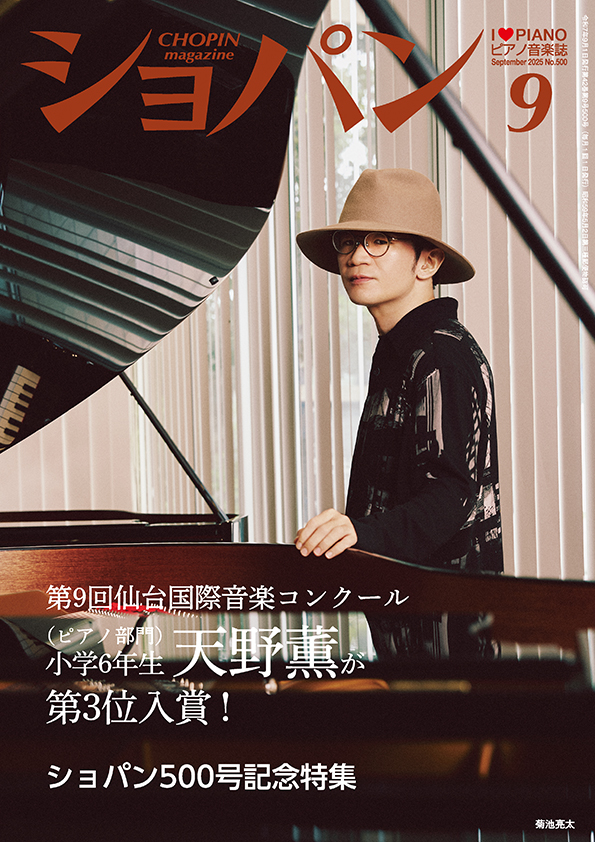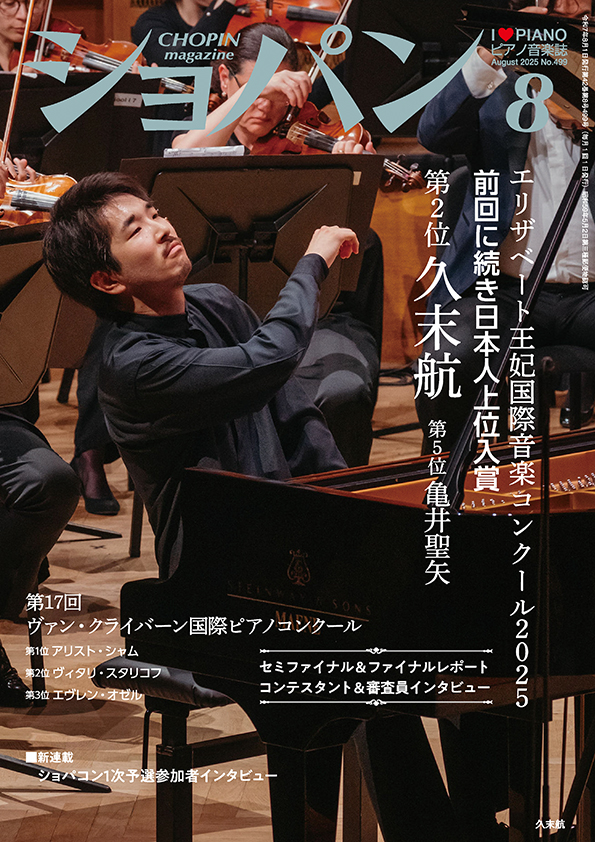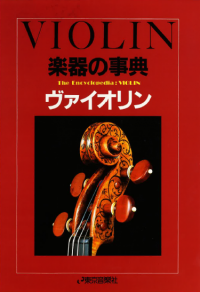
マス・プロとマス・セール
19世紀においては、その以前の王侯貴族や城主などの富裕階級のためにヴァイオリンを製作した状態から、庶民や大衆のための楽器の製作の必要性が多くなるという経済状況の変化が生じたため、伝統的な熟練した手工業による製作法では、メーカーたちは必ずしも成功が保証されないという状態となった。もちろん、伝統的な卓越した製作技術を受け継いだメーカーもいた。
しかし、彼らはその高価な楽器の販売ルートを持たずに悪戦苦闘して、必ずしも経済的に恵まれた生活を送ることはできなかった。
このような時代に、新しい市場、つまり大衆や庶民に、安価なヴァイオリンを大量生産して販売しようとする傾向が現れ始めたのは当然なことである。つまり、産業革命による、品質はともかくとして、分業あるいは分労によるマスープロおよびマスーセールの傾向が各国で現れ始めた。
そのため中世からのギルド制つまり厳格な職人組合の世襲制から解放され、ヴァイオリンの製作は、伝統的な技術を守る優れた手工品と利益追求を第一目的とする大量生産方式に分れたのである。
後者の方式では、原材料の選択などはほとんど無視し、各部品を分業方式あるいは各家族で作り上げ、これを集めて、他の工業製品と同様に組み立てて完成するものであった。
これらの大量生産方式のヴァイオリンの製産地としては、ドイツのミッテンヴァルト、マルクノイキルヘン、クリングンタール、フランスのミルクールおよびボヘミアのグラスリッツ、シェーンバッハが挙げられる。
これらは、いずれも、森にかこまれ、他の産業がほとんどない小さな村や町であるが、19世紀から20世紀初頭にかけての、世界のヴァイオリンの生産を支えたのである。
ミッテンヴァルトは、有名なクロッツー家によって、優れた手工品の名器と同時に、安価な楽器が大量に作られたと伝えられ、マルクノイキルヘンでは、当時、25のメーカーたちが工業的にヴァイオリンを大量に製作しており、さらに、ミルクールでは、ディディエール・ニコラとよばれるメーカーだけでも、1820年代に、600人以上の従業員を抱えていたと記録されている。
これらの生産地は、極めて低廉な価格の楽器を、それぞれ年間生産数が数千本に達し、特に19世紀の末期から20世紀の初頭の頃は、当時の世界的なヴァイオリンのブームに支えられて、莫大な数の弦楽器を作り出し、ヴァイオリンの市場を支配したのである。
この影響は極めて大きく、手工品のヴァイオリンーメーカーたちは、価格面で立ち打ちできなくなり、生き残る途が至難な状況に追い込まれた。
彼等は、致し方なく、他人の作った楽器を販売したり、修理や調整の仕事をしたり、時折りハンドメードのヴァイオリンを作ったりして生き延びようともがいたのである。
楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第1章 32 ヴァイオリンのブーム
▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次