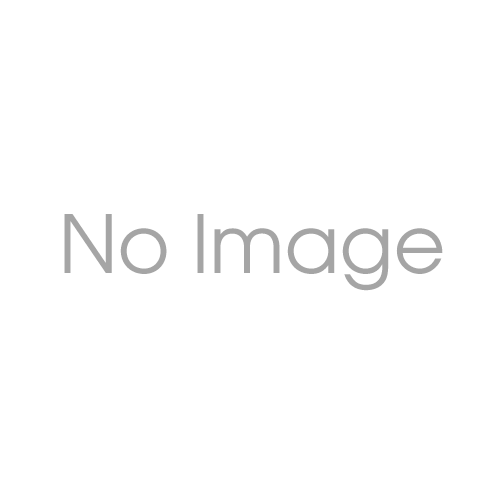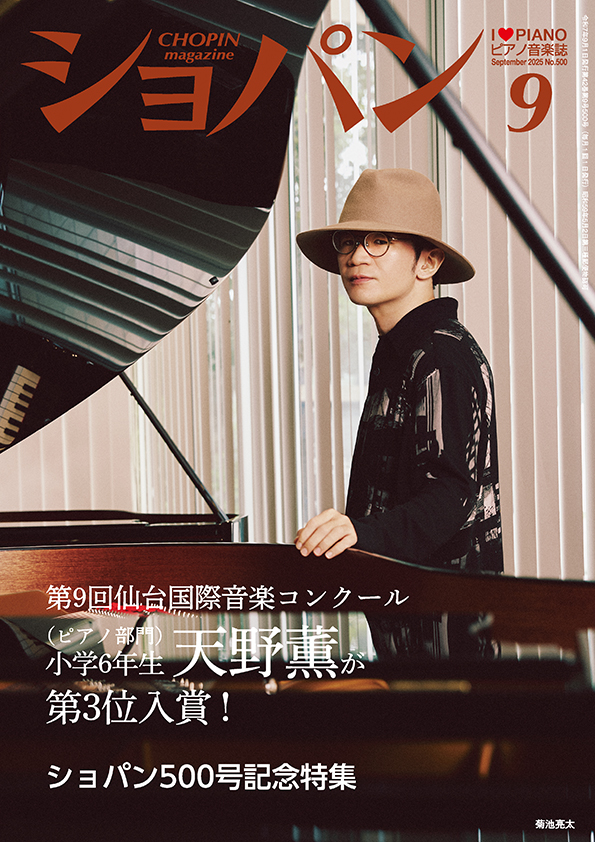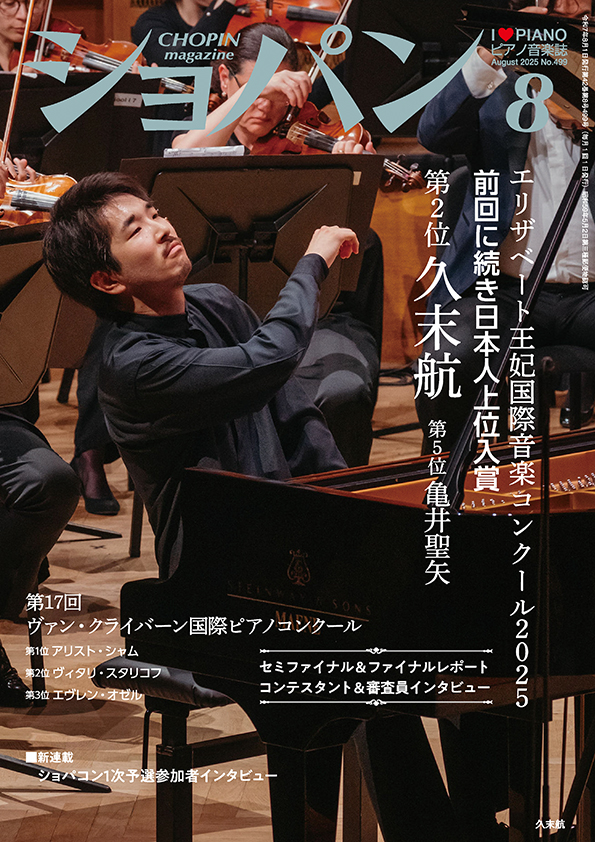[画像]イタリアの彫刻画 1784年
プラハ国立博物館
プラハ国立博物館
その衰退
その反面、クレモナの製作者がスタイナー型の楽器を受け入れなかったのが、その衰退の原因であったとも云われている。幾多の天才的な名工を抱えながら、この時期にクレモナの名器の生産は次第に衰え始め、やがて復活不可能な状態に至ってしまったのである。ヴァイオリン製作の秘法も、クレモナのニスの秘密も掻き消えてしまった。
ストラディヴァリがこの世を去った際に、2人の息子に遺した楽器の数は百本もあったと伝えられる。現在の価値から考えると天文学的な金額である。
18世紀の末に、楽器のコレクターであった、コジオーデーサラブエ伯爵がこれらを買い求めるまで、この莫大な数の宝物は長い年月放置されていたのである。
(注)、ストラディヴァリは大金持で、各国の王様や貴族などの依頼を受けて最高な楽器を作り続けたという。つまり、当時は、現在の大量生産の製品とは違って、大部分が受註生産であったのである。
なお、クレモナの名器の製作者は、他のヴァイオリンの生産地、例えばクロッツが始めたミッテンヴァルトなどと違って、販売ルートを持たず、さらにその値段が高価なものであった。
高価で、しかも、販売先がなく、流通経路も情報伝達つまり現在でいうP・Rもなかったし、その上、ヨーロッパ諸国ではスタイナー型の楽器が人気を博していたので、いわゆる宝のもちぐされとなってしまったのは理解できる。
その当時、ヨーロッパ全土にヴァイオリンの普及が進み、安価な楽器が数多く販売された。クレモナのヴァイオリンは高価でしかも輸出ルートを持たなかったのでせっかくの名器もあちらこちらで眠ってしまったのである。
(注)、十九世紀にルイジ・タリシオ(1790〜1845)というヴァイオリンの鑑定の奇人が現れ、イタリアの各地の寺院その他に眠っていたオールド・ヴァイオリンの名器を掘り起し、アルプスを越えて、花の都パリに持ち込み大もうけをしたという面白い話か残されている。
その後、1500本とも3000本とも伝えられているストラディヴァリウスの名器はクレモナに全く無くなり、現在残っている楽器は、その後、クレモナの名誉のために買い戻し、市役所に保存されているわずか1本(1715年作、クレモネーゼ)だけである。
クレモナがこのような状態になっただけではなく、他のイタリアの偉大なメーカーもその影響を受けた。
18世紀の中頃までに、ヴェニス、フイレンツェ、ボローニャおよびローマなどのヴァイオリン製作者たちも衰退を余儀なくされた。
ナポリのガリアーノーファミリーだけは例外的に、1800年頃まで栄え続けた。
しかし、そのヴァイオリンは、価格の上でも品質的にも、黄金時代のクレモナの諸名器とは較べようもないものであった。
同様な状態でミラノのメーカーたちも何とか生き延びた。しかしながら、1780年頃には数少ない製作者たちだけが残る状態となった。
1775年頃までには、ヨーロッパ各国の音楽の文化センターなどは、それ自体のヴァイオリンの生産地を持つようになり、その生産地ではスタイナー・モデルの楽器が作られた。
楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第1章 19 ヴァイオリンの構造の改良
▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次