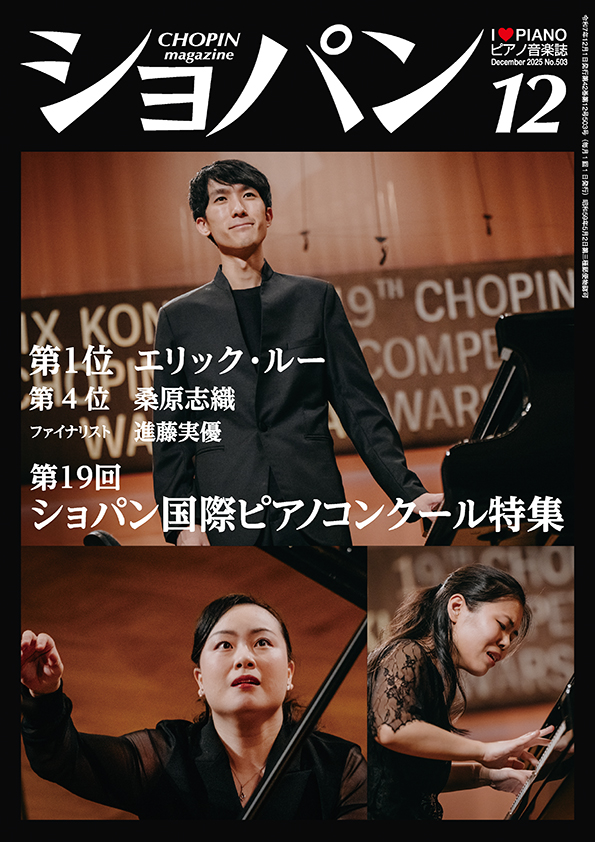オペラ名作217 もくじはこちら
詳解 オペラ名作217 野崎正俊 より
日本オペラ
O. Shimizu, Daibutsu-Kaigen 1970
大仏開眼[全3幕]清水脩作曲
❖登場人物❖
葛城郎女(S) 国中連公麻呂(Br) 牛麻呂(Br) 大神杜女(A) 秦安彦(T) 佐伯弁麻呂(T) 傀儡女(A) 大僧正行基(B) 高市眞国(Br)他
❖概説❖
作曲者清水脩にとって九作目のオペラである。奈良時代後期の聖武天皇の平城京、東大寺の毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)(大仏)造営をめぐり、時の朝廷内の政治権力の争奪や仏教界の主導権争いなどを背景にした壮大なオペラである。芸術祭主催公演として文化庁からの委嘱作品として作曲された。
第一幕
第一場 天平19年(747年)2月20日、山背国木津部落の路傍。相次ぐ天災や疫病の蔓延による社会不安を鎮めようと、聖武天皇は天平15年に大仏建立の詔(みことのり)を発したが、技術上の難点や反仏教派の妨害もあって工事は進捗しない。労役に徴集された農民の不満の声に、大僧正行基は事態を心配する。
行基は造営中の大仏の原型が何者かの手で破壊され、落胆した造営長官託陀真玉が行方不明になったので、代わりに弟子の仏師国中連公麻呂が任命されたと公麻呂に伝える。公麻呂が感激していると託陀真玉の娘の葛城郎女と弟子の佐伯弁麻呂が駆けつけ、託陀真玉が自殺したのは公麻呂のせいだと罵る。
第二場 天平19年5月5日、春日山裾の森はずれ。大仏建立推進派の藤原仲麻呂と反対派の橘奈良麻呂の対立が激しくなる。仲麻呂は宇佐八幡の巫女大神杜女に命じて奈良麻呂を呪い殺そうとするのに対して、奈良麻呂は不満分子を操って大仏建立工事を妨害しようとしている。
恒例の花鎮祭の日、若い男女が春日山裾の野原で歌い踊り終わったところに、大神杜女と奈良麻呂の手下の秦安彦が連れ立って現れる。杜女は自分に好意を寄せる安彦を唆(そそのか)して、呪詛に使う奈良麻呂の毛髪と黒犬の髑髏(どくろ)を盗ませる。望みの品を受け取った杜女は、物凄い形相で奈良麻呂を呪う祈祷を始める。安彦は主人に対する裏切りに呵責(かしゃく)を覚えながら、恋する杜女に奈良麻呂の陰謀の一端をついしゃべってしまう。杜女はそれを聞きながら、愛する仲麻呂に思いを馳せるが、にわかに天がかき曇るので、急いで森の中に入る。
嵐が去ると再び花鎮祭のにぎわいになる。人々が去ったところに公麻呂が現れ、大仏建立がはかどらず、また華厳教義が広まって行くので、行基が説くように日本人の姿をした大仏が正しいのかわからなくなったと一人悩む。
そこに葛城郎女と弁麻呂が姿を現す。弁麻呂は、奈良麻呂から大仏建立を失敗させたら次の造営長官に任命すると言われたことを葛城郎女に打ち明け、その時は結婚してほしいと迫るが、彼女が承諾しないので捨て台詞を吐いて去る。
葛城郎女の前に公麻呂が歩み寄り、自分は「大仏は世界の御仏」という託陀真玉の考えが正しいように思うので、お父上の遺業を継いで建立に励むと言う。そこに行基の死が伝えられる。
第二幕
第一場 天平勝宝元年(749年)2月20日、弾正台の裁きの場。前幕から二年後、杜女が奈良麻呂を呪殺しようとした罪で、手助けをした安彦とともに裁きの場に引き出されている。弾正台の役人に対して杜女は口を割らないので、安彦を拷問しようとすると、彼は舌を噛み切って自殺する。安彦の懐の訴状には大仏建立を妨害しようとした奈良麻呂の陰謀が記されているので、裁きは突然中止される。
第二場 天平勝宝元年7月15日、毘盧奢那仏鋳造の場。聖武天皇が病気がちなので大仏造営工事は急ピッチで進められているが、最後の段階で銅千斤の不足が明らかになる。そこに葛城郎女が駆けつけて、父の遺作の銅像の提供を申し出るので、さっそく鋳造を再開する。
公麻呂が報告のためにその場を去っているすきを見て、奈良麻呂に加担する仏師高市眞国が湯口を開けて銅を流し出そうとするので、仏師柿本男玉と争いになる。その間に弁麻呂が湯口を開けてしまうが、急遽引き返した公麻呂が自ら体を張って銅の流出を防ぐ。計画が失敗した眞国と弁麻呂は逃げ出す。瀕死の火傷を負った公麻呂は残った銅で世界に無双の大仏を完成させるよう男玉に叫んで息を引き取る。公麻呂の体に取りすがって慟哭(どうこく)する葛城郎女の声のうちに湯口は開かれて、銅汁が取り出される。
第三幕
第一場 天平勝宝四年(752年)4月9日、大仏殿の裏手。ようやく完成した大仏の開眼供養が行われている。仮設の塀の外に押しかけた群衆の「南無、毘盧奢那仏」という声が聞こえる。
塀の内側では、牛麻呂が傀儡女とこれまでの苦労話などをしている。そこへ儀式に参加する男玉が通りかかって、大仏殿のほうに向かう。その時群衆の圧力で塀が崩れ、なだれ込んだ群衆の波に飲み込まれた牛麻呂は一人置き去りにされる。
第二場 天平勝宝4年4月9日、大仏殿のうち。大仏開眼の供養も終わった夜ふけ。牛麻呂が見回りのために仏殿に入ると、突然かん高い笑い声がして古い恋歌が響きわたる。そして悲惨な死を遂げた公麻呂をまのあたりにして気が狂った葛城郎女が、大仏の掌に登って公麻呂をかき口説いているのを見る。牛麻呂は葛城郎女の気持ちを察して、そっと立ち去る。葛城郎女は大仏か公麻呂か区別がつかずに、空しく歌い舞うのみだった。
Reference Materials
初演
1970年10月2日 日生劇場(東京)
原作
長田秀雄の同名小説
台本
清水脩、岡本一彦/日本語
演奏時間
不詳
ショパン別冊 詳解オペラ名作217 2013年12月発行 無断転載禁止