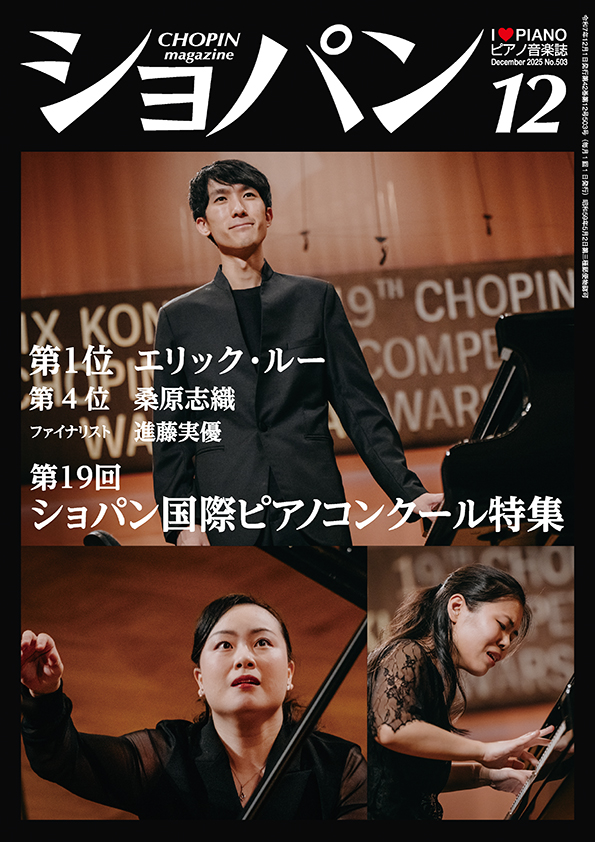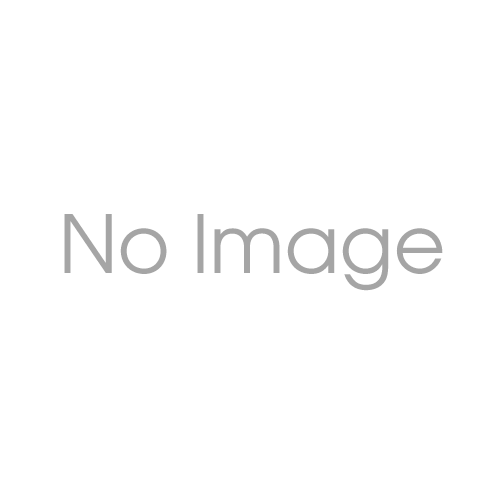
第2の時期(1722~1728)―暗中模索の時代
24才から30才までの時代である。
ガルネリ一族は家庭内が円満でなかったらしく、彼も、1723年、つまり25才の時に父のもとを離れて独立している。
この時代のデルージェスは、理想の音色を求めて、さまざまな形態のヴァイオリンを試作している。それらのなかには、やや小型のもの、胴が少し膨んだもの、ストラディヴァリウスに似てウェストが締まったもの、裏板が板目取りのもの、グロテスクな形態のものなどがあった。彼は、新しい音色の創造を求めて急ぎ過ぎたといわれている。
現在まで残されているデル・ジェスのラペルのついた楽器の最古のものは、1726年作のもので、そのラベルには、さきに述べた、I.H.S.のモノグラムと十字架のマークがっけられており、彼は生涯これと同じラベルを使い続けている。
1723年から1726年までは、何をしていたかは全く解っていない。
その頃のデル・ジェスには、アマティやストラディヴァリのような、王侯貴族からの注文は全くなく、庶民のための楽器を作り続け、逼迫した資金状態のために、売り急いだと想像される。
当時の彼には、アマティやストラディヴァリと違って、綿密に楽器を作り上げる余裕などは全くなく、スクロールを半分仕上げて次のヴァイオリンの製作に移るというような状態で、大急ぎで仕上げたため、その形は大小さまざまで、f字孔でさえ長いもの短いものと変化し、左右不対称なものや曲ったものまであった。しかし、ニスは、透明で軟らかく、美しい金褐色あるいはシェードのついたブラウン色に仕上げられていた。
これらの楽器には、ヴァイオリン王国であったクレモナの伝統技術に従わず、板の厚さを変えて理想の音色を求めようとする苦闘の跡がうかがえる。その極端な例としては、大きい音を出すために、胴板の中心部を厚くし過ぎて、音色の輝やかしさを失ってしまったヴァイオリンもある。
現在まで残されたこの時代の楽器のなかの数本には、彼の楽器に特有な、音色の力強さ、輝やかしさおよび浸透力のすべてを失ったものもある。
デルージェスは、この時代に、貧乏神と戦いながら、理想のヴァイオリンを求めてさまよい、次の黄金時代の超人的な楽器を作り出すための基礎を固めたといえる。
この頃のデルージェスの作品にはユニークなヴァイオリンが多く、コレクターたちの垂涎の的となっていると伝えられる。
1725年に、珍らしくも、デルージェスがミラノのスカラ座のコンサートーマスターに売ったヴァイオリンが記録されている。このユニークな楽器は、のちにアメリカのヴァイオリン奏者の手に渡ったが、不幸にして、1920年に、演奏旅行中に盗難に遭い、行方不明となっている。
楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎2章 46 第3の時期(1729~1743年)ー黄金時代
▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次