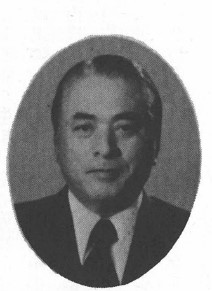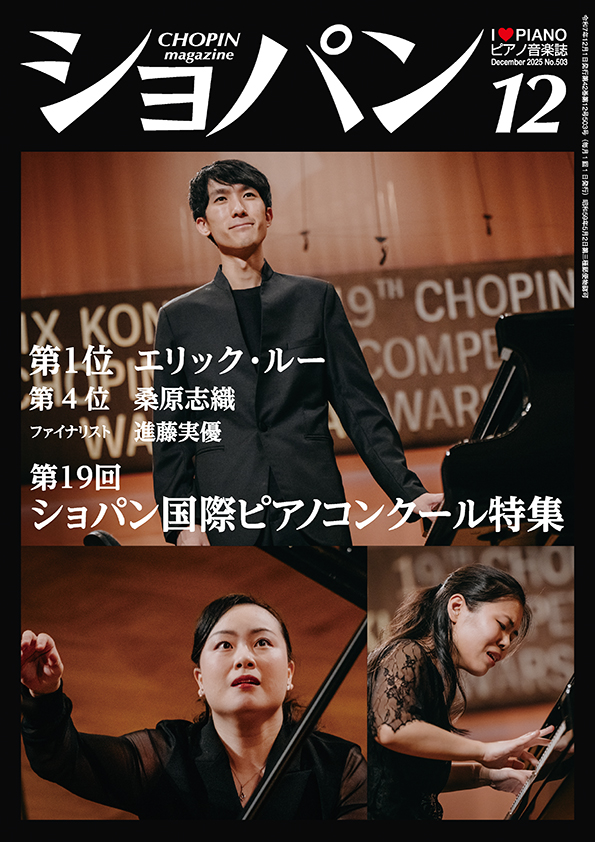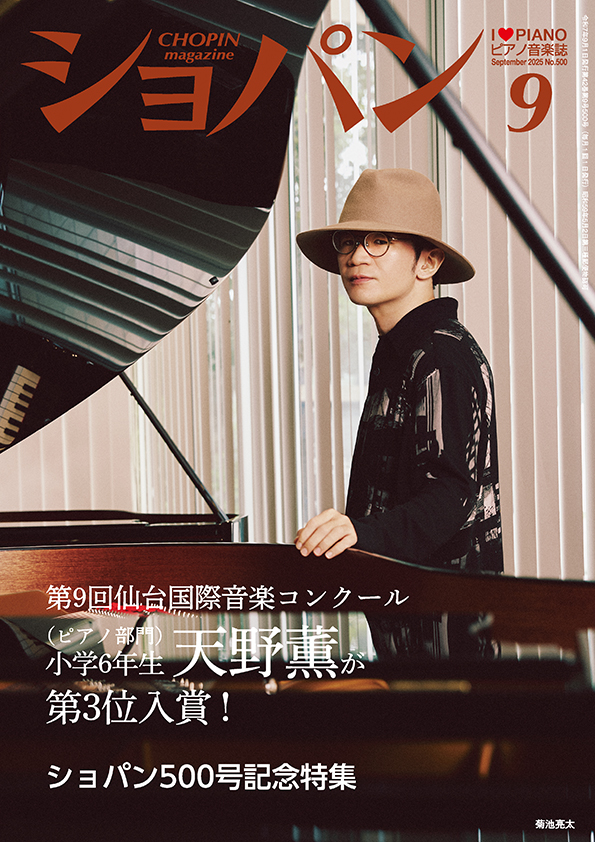[画像]1770年にロンドンで出版されたJ.C.バッハのチェンバロあるいはピアノソナタの楽譜のタイトルページ。
ピアノ時代の到来
ピアノの発展普及に油を注いだもう一つの理由は、世界的に交響曲、オペラ、オラトリオ、歌曲、聖歌、讃美歌などの音楽が一般の人々の間に普及していったことだろう。これらの各種の音楽がポピュラー音楽とともに急速にピアノ用に編曲され始め、ピアノという楽器は他のあらゆる楽器よりも優越したものとして、19世紀以後の黄金時代に向かうのである。
18世紀の終末においては、従来のチェンバロと、新しく出現したピアノとの優劣に関する論争が盛んに行われていたらしい。
パリのノートルダム寺院のオルガン奏者であり、フランスの作曲家であったバルバストレは、ピアノメーカーに対し「無駄なことは止めた方がいい。成り上がり者のピアノが帝王の位にあるチェンバロに勝てるはずがない」といましめているし、有名なボルテールは、1774年に、ピアノのことを「ボイラーメーカーの楽器である」とけなしている。
また、1782年にドイツで出版された音楽便覧では「ピアノはチェンバロに比べた場合、音色に光彩と陰影を持ち、感情表現の点においては優れているが、クラビコードと比較すると、中音部の音の美しさを欠き、洗練されたデリケートな音色の美しさがない」と書かれている。
ピアノがチェンバロやクラビコードを鍵盤楽器の王位から追い落とすことはなかなか容易なことではなかったのである。
チェンバロによる音楽からピアノ音楽への推移は、楽譜出版の記録によって正確にたどることができる。当時の楽譜の出版はほとんどイギリスによって占められており、その1750年以降をたどると次のような結果となる。
1750〜80年 これ以前にはピアノに関する出版物は全くなく、この30年の間に300種類近くの鍵盤楽器の楽譜が残されているが、ピアノに関するものは1750年頃からボツボツと現れ始め、1770年以降ではピアノとチェンバロとの兼用の楽譜がチェンバロ専用のものより多くなっている。
1785年以降 チェンバロの楽譜はほとんど消え失せ、ピアノとチェンバロとの共用の楽譜がほとんどを占めている。その理由は楽譜出版の商業的な目的によるものだろう。
1800年 38冊の楽譜集のうち、チェンバロ専用のものは全くなく、3冊がチェンバロとピアノの兼用で、他の35冊はいずれもピアノ専用となっている。
これらの楽譜出版の記録を見れば、ピアノという楽器が18世紀の末期に、チェンバロを凌駕(りょうが)して、急激に一般に愛好され始めたことが明らかとなる。しかし、鍵盤楽器以外の室内楽や声楽の楽譜では、その当時、依然としてチェンバロのためのものがほとんどを占めており、結局、演奏会用の楽器としてはチェンバロが優位を保っていた。
ピアノが演奏会用の楽器として使われ始めたのはいつ頃からであるかは判然としていない。しかし1767年に、当時ロンドンにおいて有名な作曲家兼演奏家兼著述家であったチャーレス・ディブデンが、慈善興行のための歌曲コンサートで「ピアノフォルテという新しい楽器を使って」と題してピアノで伴奏をしたという記録がある。これが多分、ピアノを演奏会用に使用した最初であろう。その翌年の1768年にJ.C.バッハがツンぺのピアノを使って公開演奏を行っている。なお、ピアノ曲としてはこれより二年前にバートンの10曲のソナタが出版されている。
その頃のヨーロッパのピアノの生産台数は全くわからないが、イギリスのロンドンにおけるものだけは記録として残されている。それによれば、当時、ロンドンだけでも45軒のピアノメーカーがあり、有名なブロードウッドは1780年から1800年までに6千台のスクエアピアノと1万台のグランドピアノを生産したという。
このようにして、当時の有名なチェンバロメーカーであったイギリスのカークマンやフランスのヘスなども、やがてピアノへの転換を余儀なくされていったのである。
ロンドンのジョン・ブロードウッド・アンド・サンズが、1883年に作ったグランドピアノ。
ブロードウッドが1817年に作り、ベートーヴェンに贈ったグランドピアノ。
このような美しいチェンバロが18世紀に次々と姿を残して行った。
ジョン・ブロードウット
ブロードウッドが1840年に作った6オクターブのキャビネットピアノ
改訂 楽器の事典ピアノ 平成2年1月30日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第1章 12 18世紀におけるアクションの発達
▷▷▷楽器の事典ピアノ 目次