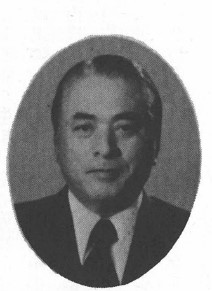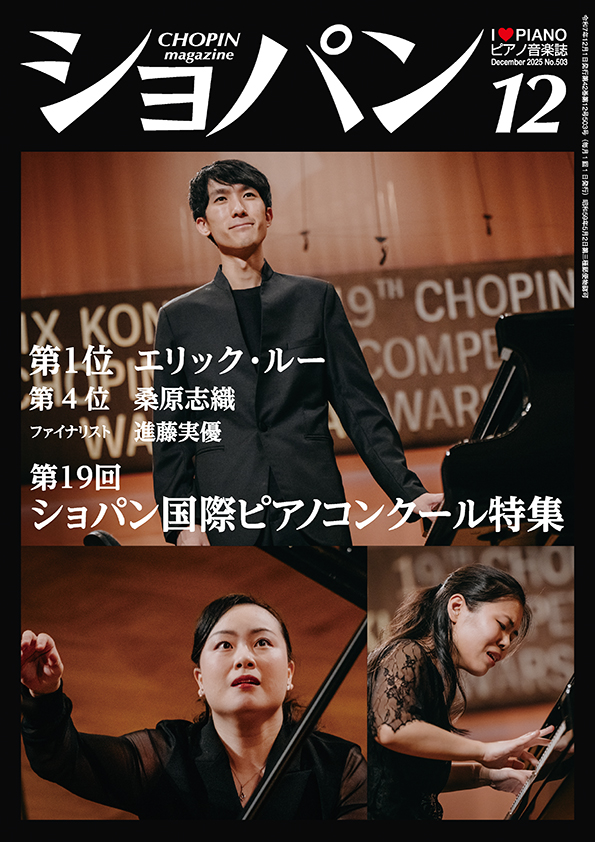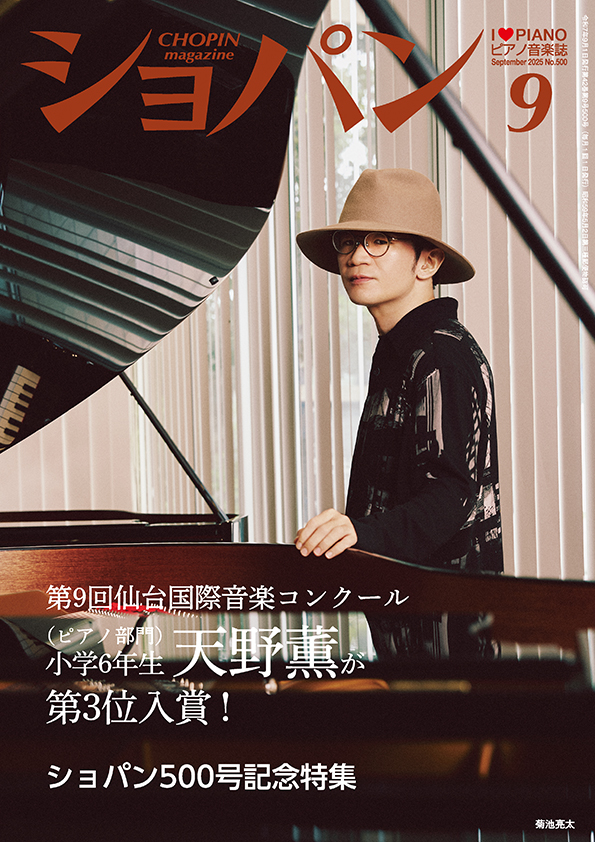[画像]ウィーンの宮廷ピアノメーカーであったコンラッド・グラフが1829年に作ったピラミッドピアノ。
ピアノの本質から外れた楽器
19世紀におけるピアノは、その使用目的、および構造などの諸点において、現在の楽器とはいささか異なった性質を持っていた。19世紀のピアノはハウスホールドオーケストラとして栄えていったのである。ピアノという楽器はオルガンのように悠久と言われるほどの長い歴史を持っていない。そのため、ロマンティックな、またシンフォニックな音楽の流れの影響をたちまち受けて、正統的な音楽からかけ離れたものとなっていったのである。つまり、家庭の中のオーケストラとして使うという誤った方向性に毒され、当時のバッハを忘れたロマンティックオルガンの隆盛と同様に音楽美学的な本質から外れ、エキセントリックな楽器へと転化してしまった。そのためにピアノの本質から外れたものが続々と作られるようになった。
継続音の出せるピアノ 当時、ピアノの最大の欠点は継続音が出せないことにあると考えられていた。もっとも、この欠点は現在でも見逃せないことであるが、18世紀の作曲のほとんどはオルガンとチェンバロのためのものであったので当時の人びとにとってはさらに堪え難いものであったのであろう。そこで、レペティションではなしに、サスティントーン(継続音)をピアノで出すために、次のようなさまざまな工夫が考え出されたのである。
摩擦音による方法 継続音を出す最初の試みはニュールンベルグのピアノ工場でなされたと伝えられているが、具体的にはどんなものであったかはっきりしない。
18世紀から19世紀にかけては、ピアノを鳴らすのにペダルで駆動してグルグル回る円型の木製の輪に松脂をつけて、ヴァイオリンのように、弦を摩擦する方法がしばしば試みられた。これは、ハーディガーディやゲイゲンベルグと同じ原理であるが、アメリカでは1802年にフィラデルフィアのジョン・アイザック・ホーキンスがこの種の楽器を作り、クラビオールと名付けている。この楽器はキーを押すと弦が持ち上げられて回転している輪に接触して継続音を出すようになっており、音の大小も押さえ加減によって変化させることが可能であった。イギリスでも1817年に、ブライトンのモットという音楽教師が同様の楽器を作り上げている。
トレモロ式の連続音装置 これはパイプオルガンやヴァイオリンのような継続音は出せないが、プレクトラムで演奏するマンドリンの奏法によるトレモロ式の連続音が出せるものであった。1800年にホーキンスの父親がこの方式でイギリスのパテントを取っている。
その工夫を簡単にいえば、オルゴールや自動オルガンのシリンダー(円筒型のものに無数のツノがある)に似たものを回転させて鍵盤を押さえている間、ハンマーが連続的に弦を叩き続けてトレモロ式の連続音が出せるものであった。この方式は当時の多くのピアノメーカーによって採用され、フランスのエラールやアンリー・パペもこのようなパテントを申請している。
空気の流れによる方法 この方法は空気の流れを利用して、弦を振動させて継続音を出す考案であった。ソロモンのダビデ王の時代にエオリアンハープという楽器があって、このハープを寝台の上に立てかけておいたら夜中に北風が吹いて、えもいわれぬ美しい音楽をかなでたと伝えられているが、この考案は、昔のエオリアンハープの不思議な現象から思いついたものであろう。
1828年にはエッシェンバッハがエオロディコンと呼ぶ鍵盤楽器を作り上げている。これはエオリアンハープとパイプオルガンの原理を混ぜたようなもので、オルガンのパイプの代わりに弦を張り、風圧で震動させて継続音を出すものであった。
イギリスではコンセルティナ(アコーディオンに似たリード楽器)の発明者であるホイートストンとグリーンの二人が同様のパテントの申請を出しているし、パリのアンリー・パペは弦を互いに絹糸で連結してシンパセティックトーン(共鳴音)が出せるこの種の楽器を考案している。しかしいずれの場合も弱い音しか出なかったに違いない。
トルコ音楽の影響 18世紀の終わりにロシア帝国とトルコとの間に和平条約が締結されて以来、トルコの楽器と音楽がヨーロッパ諸国に流入して広くもてはやされるようになった。楽器としてはドラム、トライアングル、シンバルが主なもので、軍隊に採用されたのを始めとして、ダンス音楽などにも広く使われ始めた。
作曲としてはモーツァルト、ベートーヴェンの「トルコ行進曲」やグルックの「アウリスのイフィゲニア」、モーツァルトの「後宮からの逃走」などでトルコ風のメロディが登場している。
そのために、ピアノにもいろいろなドラムが取り付けられ始めた。変ったものとしては、フットレバーで動かすスティックでピアノの響板を叩く方法、あるいは響板の中央に丸い穴をあけ、これに皮を貼ってペダルに連動したスティックで叩き、ドラムそっくりの音を出す方式などが考え出された。これは20世紀の20年代から30年代にかけて作られたシネマオルガンに考え方が似ているが、いずれの場合も長続きするものではなかった。
戦争と嵐の音楽の流行 1800年ごろはベートーヴェンが「交響曲第6番・
田園」を書いたように、戦争と嵐の音楽が流行していた。パリの教会のオルガンでは、大砲の音、ラッパの音、武器のざわめき、果ては負傷者のうめき声まで出したと伝えられている。ピアノでは二個のペダルがついていて、片方のペダルを踏むとサスティーンの音、他の一方はスウェルの役目を果たし、戦争の曲を弾くときはスウェルペダルを急に放すと、ふたがガチャン!と落ちて大砲の炸裂音が出るというすさまじいものもあったという。しかし、この装置は演奏者の神経と楽器をこわす以外に何の役にも立たなかった。
以上述べてきたように、ロマン派の音楽に対応した、さまざまなエキセントリックなピアノが作り出されたが、これらは俗人によろこばれた楽器で、一方ではオーソドックスなピアノ曲を演奏するための正統なピアノも着々として発達していったのである。リスト、ブゾーニ、ラフマニノフなどが弾いたピアノはほとんど現在のグランドピアノと機構が変わらぬ正統的なものであった。
 フィラデルフィアのジョン・アイザック・ホーキンスが1801年に作った"ポータブルグランドピアノ"。ベネチアン・スウェルーーパイプオルガンのスウェル装置のようなものーーなどのさまざまな工夫が加えられたものであったが、音楽的には不成功であったと伝えられている。
フィラデルフィアのジョン・アイザック・ホーキンスが1801年に作った"ポータブルグランドピアノ"。ベネチアン・スウェルーーパイプオルガンのスウェル装置のようなものーーなどのさまざまな工夫が加えられたものであったが、音楽的には不成功であったと伝えられている。 ヘンリー・パペが19世紀に作った六角型のピアノ。(イタリアのミラノ博物館)
ヘンリー・パペが19世紀に作った六角型のピアノ。(イタリアのミラノ博物館) 最も初期の形式のピラミッドピアノ。ハンガリーのウィルヘルム・シュワップ(1814〜1856)の作。形がシンメトリックで美しく、黄色の模様のデコレーションが施されている。
最も初期の形式のピラミッドピアノ。ハンガリーのウィルヘルム・シュワップ(1814〜1856)の作。形がシンメトリックで美しく、黄色の模様のデコレーションが施されている。 ベルリンのJ.C.シュライプが1820〜1830年ごろ作ったアップライトピアノ。
ベルリンのJ.C.シュライプが1820〜1830年ごろ作ったアップライトピアノ。 19世紀のイタリアのカステロ・スフォルゼンコが作ったウィーン風のジラフピアノ。レジスターを変えるピアノが5個ついている。
19世紀のイタリアのカステロ・スフォルゼンコが作ったウィーン風のジラフピアノ。レジスターを変えるピアノが5個ついている。 19世紀初頭のチェコのジラフピアノ
19世紀初頭のチェコのジラフピアノ改訂 楽器の事典ピアノ 平成2年1月30日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第2章 黄金期を迎えた19世紀・20世紀 3 多種多様なペダル
▷▷▷楽器の事典ピアノ 目次