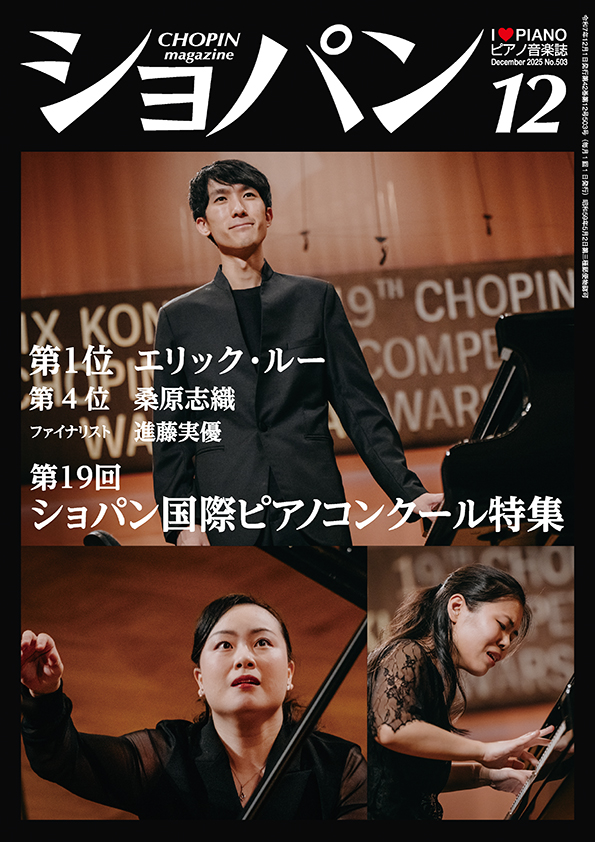オペラ名作217 もくじはこちら
詳解 オペラ名作217 野崎正俊 より
日本オペラ
M. Miki, Shunkin-sho 1974~1975
春琴抄[全3幕]三木 稔作曲
❖登場人物❖
春琴(S) 佐助(Br) 安左衛門(Br) しげ女(Ms) 利太郎(T) 他
❖概説❖
日本オペラ協会の委嘱で作曲された三木稔の代表作であり、海外にも紹介されるなど上演回数は多い。原作は会話体を含まない谷崎潤一郎の小説による。まえだ純の優れた台本と古曲を取り入れた三木稔の音楽構成力が光り、二十弦箏と三弦が効果をあげている。
江戸時代の天保年間から慶応元年にかけての物語である。大阪道修町に住む春琴は薬種業安左衛門の娘であるが、少女時代に失明してから琴と三弦の稽古に励み、一門の中では並ぶ者のない存在になっている。
丁稚で彼女の弟子である佐助は毎夜物干し台に忍び出て、春琴に対する秘めやかな恋と、彼女との出会いを回想風に歌う。春琴は佐助に厳しい稽古を課し、佐助は折檻にも近い稽古を押しつけられるのに自嘲的になり、わが身の不甲斐なさを嘆く。やがて春琴は身ごもる。春琴の両親の安左衛門としげ女は、春琴が懐妊させられた相手は佐助だと思い、否定する佐助に結婚を迫るが、春琴は一生独身を貫くことを強く主張する。
放蕩者の利太郎の父親の隠居所の庭で梅見の宴が開かれている。そこに利太郎とは同門の佐助が、春琴の手を引いて現れる。春琴と佐助の信頼厚い交情ぶりを垣間見た利太郎は嫉妬を覚える。ここで語り手によって、春琴と佐助の生活ぶりや生い立ちが語られる。
北の新地に住む少女に対して春琴は稽古をつけているが、稽古が進まず苛立たしくなって怒鳴りつける。一方利太郎は、常にもまして厳しい春琴の稽古にいじめ抜かれ、挙句の果てに撥(ばち)を投げつけられて眉間を傷つけられるので、憤然として立ち去る。佐助は利太郎の復讐を恐れるが、春琴はあくまでもプライドに固執する。
利太郎は復讐として春琴の顔に熱くたぎった鉄瓶を投げつける。彼女にとって佐助の慰めなどは役に立たず、佐助は失意の底に沈み込んだ春琴の顔を決して見まいと決心する。彼は自己犠牲の覚悟で自らの眼に縫い針を突き刺す。盲目になった佐助は春琴にいざり寄り、二人は熱烈な愛を歌う。
最後に付幕「春鶯囀(しゅんのうでん)」として、春琴が着想した歌を佐助は心魂を傾けて歌い、二人の純愛が成就したことが象徴される。
Reference Materials
初演
1975年11月24日 郵便貯金会館ホール(東京)
原作
谷崎潤一郎の同名小説
台本
まえだ純/日本語
演奏時間
第1幕40分、第2幕40分、第3幕40分
ショパン別冊 詳解オペラ名作217 2013年12月発行 無断転載禁止