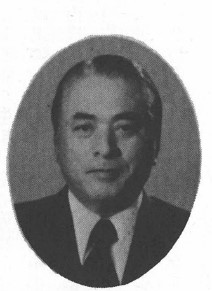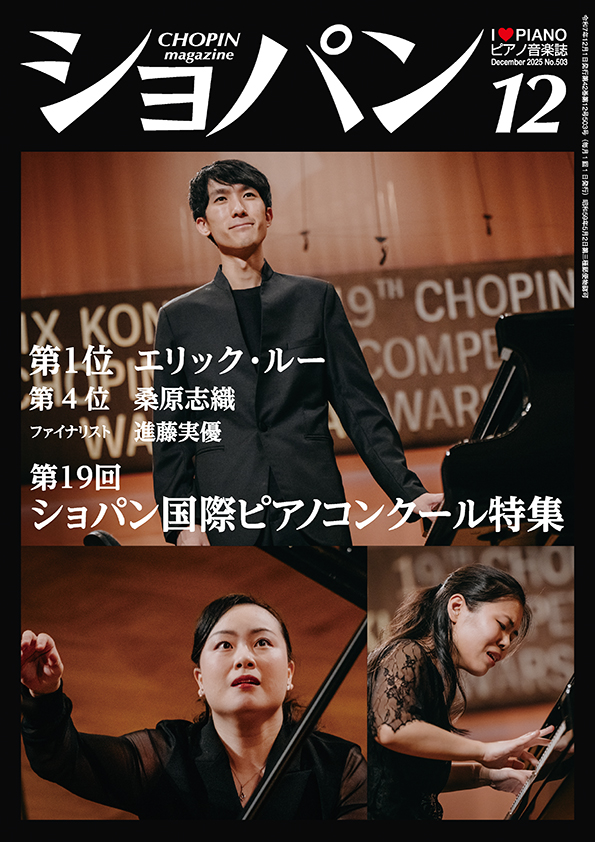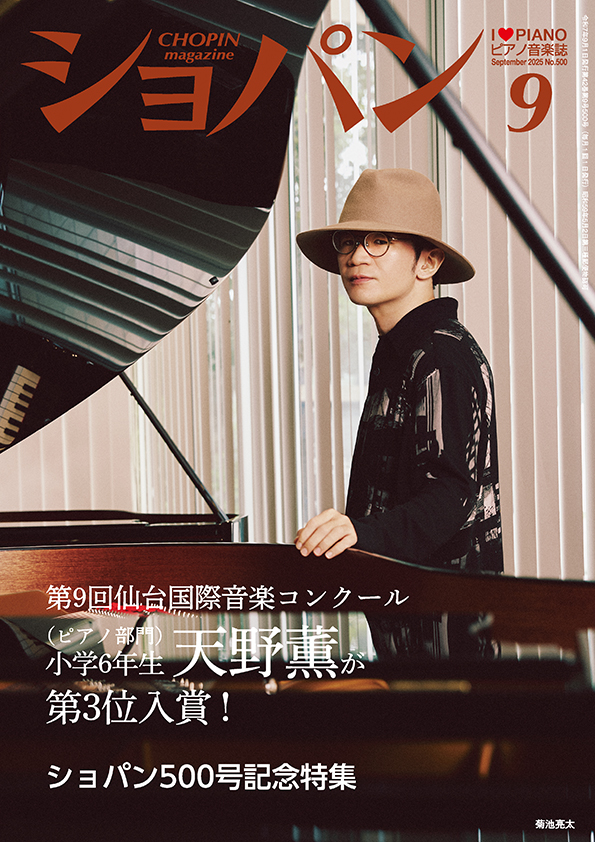[画像]ヨハン・アンドレアス・シュタイン(1728~1792)ーーウィンナアクションを発明してモーツァルトが絶賛したと伝えられているーーの息子であったアンドレ・シュタインが1802年に作ったフォルテ・ピアノ。
18世紀におけるアクションの発達
ピアノの最も単純な形式のアクションは "モップスティック" あるいは "オールドマンズヘッド" と呼ばれるもので、キーの端に差し込まれた真ちゅう線の先端につけられた皮製のクッションがハンマーをたたくことで動かす方式であった。
しかし、このアクションも弦を打ち破ったり、ブロッキンクを起こすことが多かった。この種のアクションが1800年頃のイギリスのスクエアピアノおよび1770年以後のドイツの楽器に多く使われている。このハンマーアクションの調整はまことに難しく、モップスティックが長過ぎるとブロッキングを起こし、反対にこれが短か過ぎると音が出なかったと伝えられている。
原始的アクションはさまざまな欠陥を持っており、それを補うためには、どうしてもエスケープメントをつけざるを得なかった。エスケープメントとは、ハンマーが弦に近づく直前にその駆動装置から外れて自由になり弦を叩いてはね戻る仕掛けである。このエスケープメントを備えたアクションは、ピアノの発明者であるクリストフォリがすでに彼の楽器につけてはいたが、これは完全なものではなく、のちにダンピング装置(音を消すダンパー)と併用されて、モーツァルトが好んだと伝えられるウィンナアクションへと発展していった。
エスケープメントの装置は、実際には有名なバロックオルガンのメーカーのジルバーマンの弟子であったアンドレアス・シュタイン(1728〜92年)によって発明されたと伝えられており、彼の作り出したアクションが彼の娘のナネッテによってウィーンにもたらされ、ウィンナアクションと呼ばれるようになったのである。
その当時のウィンナアクションのつけられた楽器、つまりモーツァルトやベートーヴェンなどが弾いたピアノがどのような音を出したであろうかということは極めて興味深い。「昔を今になすよしもがな」という言葉があるが、音楽と楽器の世界ではそれが可能なのである。1951年に、イギリスの音楽協会の会合でこの実験が行われた。180年以前のアンドレアス・シュタインのピアノで演奏が試みられたのである。このピアノの響板はわずか3ミリという薄さで、機能は完全なものであったが、その音量は極めて小さく、ピアノソナタやごく小編成のストリングオーケストラの伴奏でピアノ協奏曲が弾ける程度の、チェンバーコンサートにしか使えないものであったという。しかし、その反面、音色は天国的に美しかった。
ただ残念なことには、180年も前に作られたピアノでは、ハンマーの皮が古くなったり酷使されていた場合、その音色が金属的なものとなるため、果たしてモーツァルトの時代にどのような音色が好まれたかは、正確には知ることができない。
ピアノのアクションも18世紀の終わり頃にはシングルアクション、ダブルアクションおよびウィンナアクションの三種類が登場していた。
 ハイドンが絶賛したという、ウィーンのヨハン・シャンツが1800年頃に製作したグランドコンサートピアノ。当時ウィーンに住んでいたホフラス・クレイレが愛蔵していたもので、ベートーヴェンもシューベルトも彼を訪れてこの楽器を演奏したと伝えられている。マホガニー製でブロンズを細工したナポレオン時代風の飾りがつけられている。
ハイドンが絶賛したという、ウィーンのヨハン・シャンツが1800年頃に製作したグランドコンサートピアノ。当時ウィーンに住んでいたホフラス・クレイレが愛蔵していたもので、ベートーヴェンもシューベルトも彼を訪れてこの楽器を演奏したと伝えられている。マホガニー製でブロンズを細工したナポレオン時代風の飾りがつけられている。 ウィーンのコンラッド・グラッフが1820年に作った王朝風の飾りがついたグランドピアノ。ウォルナット製で、ペダルは5個ついており、ペダルの部分にギリシャ神話のオルフェースの彫刻がつけられている。グラッフはベートーヴェンと親交があり、このピアノはベートーヴェンが最後に持っていたものと伝えられている。
ウィーンのコンラッド・グラッフが1820年に作った王朝風の飾りがついたグランドピアノ。ウォルナット製で、ペダルは5個ついており、ペダルの部分にギリシャ神話のオルフェースの彫刻がつけられている。グラッフはベートーヴェンと親交があり、このピアノはベートーヴェンが最後に持っていたものと伝えられている。改訂 楽器の事典ピアノ 平成2年1月30日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎第1章 10 ピアノの生誕と発達の歴史
▷▷▷楽器の事典ピアノ 目次