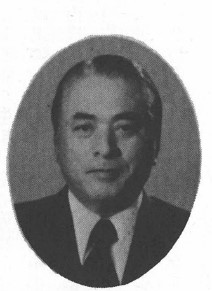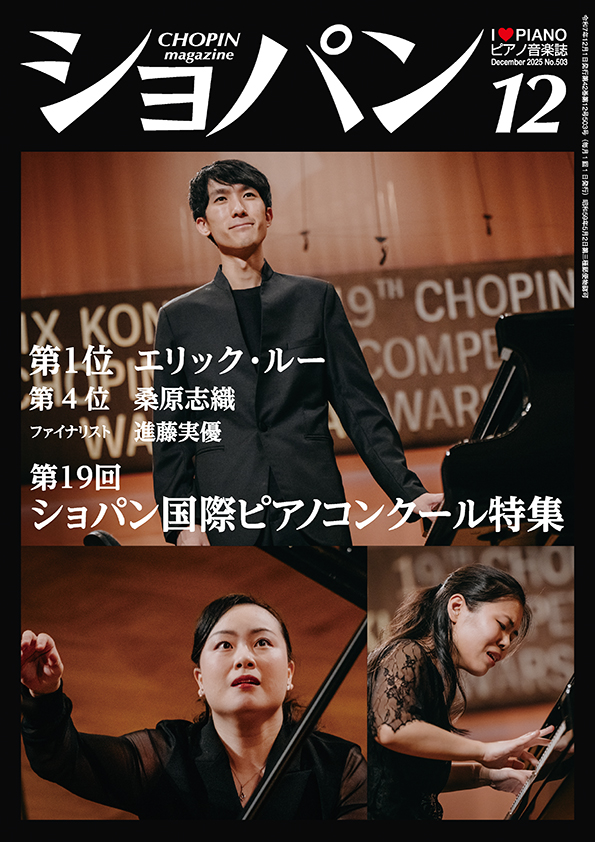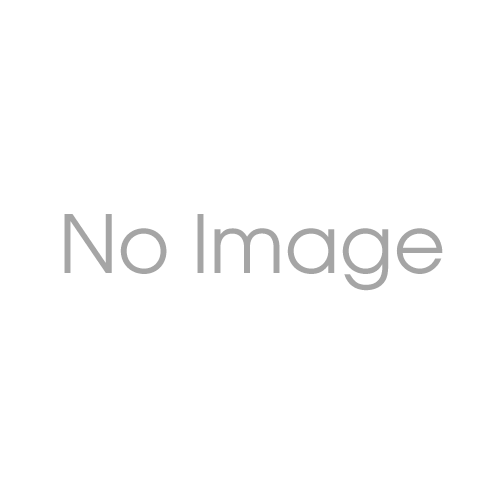
誕生に関する音楽的な背景
十八世紀までの音楽の傾向は、当時300年にわたって繁栄してきたチェンバロがピアノの誕生によって衰退していく必然性を暗示している。十六世紀の終わり頃に、イタリアの知識人たちが集まって、「カメラータ」ーー“同志”という意味、文学者と音楽家の集まりーーとよばれるグループを作り、古代ギリシャ劇の復興を目指して独特な音楽形式を作り出した。
「カメラータ」の音楽家たちは、メロディが積み重ねられ、編み込まれさらに助け合うというルネッサンス時代のポリフォニック形式をの表現法を嫌い、レシタティーボ(歌唱法)とよばれる、和音の伴奏のついた新しい音楽形式を創り出した。つまり、メロディのいくつかが揺れ動き、流れそして交叉するものから、和音による伴奏でメロディを美しく飾る方式の音楽へと転換したのである。
その代表的なものが、最初のオペラとして伝えられている、「ダフネ」と「ユーリディース」であった。
オペラによって生み出されたボーカル・スタイルの音楽は、その当時としては奇怪なイノベーションであった。人間のあらゆる喜怒哀楽の感情が如実に表現されるようになって、それ以前の、神々しい抽象的な宗教音楽などは影が薄くなってきた。
声楽には、あらゆるテクニックが使われ始め、クレッシェンド、ディクレッシェンド、トリル、ビブラートおよびダイナミックなアクセントを始めとして、極端な場合、あえぎ、息切れ、あるいはすすり泣きに至るまでの表現方法が用いられたのである。
発声技術の変化は諸楽器の性能にもその影響を及ぼし、演奏法も大幅に変わった。特に、ローマのオーケストラは、ダイナミックな表現法と、音のグラデーションを出すことに熱中した。
チェンバロがその黄金時代を迎えたのは、クープラン、ラモー、J.S.バッハ、ヘンデルおよびスカルラッティなどが活躍したルイ王朝時代であった。これらの大作曲家たちはチェンバロの性能を最大限に引き出したのであるが、その頃、音楽の嗜好はすでに変っていたのである。
J.S.バッハの音楽は新旧融合の形式をみごとに表現したものであった。しかしながら彼の音楽は、現在ではバロック音楽の最高なものといわれているが、その生存中には時代遅れであると考えられていた。バッハは1750年にこの世を去っているが、その頃を境にして、新旧の音楽は交代し、ポリフォニーは消え去ったのである。
クープランは、1713年に出版された、彼のチェンバロ曲集のイントロダクションに次のように述べている。
ーーチェンバロは、その音域の広さと音色の輝かしさの点においては、申し分のない優れた楽器である。しかし、この楽器では、残念ながら、音の強弱を出すことが不可能である。もし、この楽器に表現力を与えることに成功する人が現れたら、私はその功績に対して絶大の感謝を捧げたいーー。
しかし、クープランは、フローレンスでクリストフォリがピアノフォルテを作り出したことは知らなかった。
ピアノフォルテは、その誕生の当初では、チェンバロを凌駕することはできなかったが、その後の半世紀の間に、表現力の大きいボーカルや他の諸楽器と共に、チェンバロのクレッシェンド、ディミニュエンドおよびダイナミックなアクセントが出せないという欠点をあばき続け、ついにその滅亡に追い込んだのである。

“チェンバロ” ヒエロニムス・ハスが1740年に製作した作品と思われる。全体は模造のべっ甲で飾られ、ふたには女性にチェンバロを贈るハスが描かれている。

“ダルシマー” 17世紀のフランスの銅版画
改訂 楽器の事典ピアノ 平成2年1月30日発行 無断転載禁止
▶︎▶︎▶︎序章 4 誕生の動機
▷▷▷楽器の事典ピアノ 目次