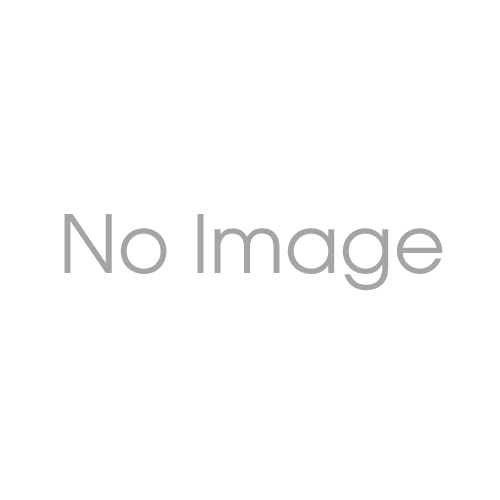
昭和59年(1984年)1月1日発行「ショパン」創刊号より転載
華麗なる世界“女流”音楽史
“女流”作曲家とピアニストの系譜 上野学園大学助教授 船山信子
なぜ“女流”は特別視されるのか
やっと紹介されはじめた女流作曲家たちの作品
「どうして音楽史上、女性の作曲家がいないのだろうか?」という素朴な疑問は、西洋音楽にたずさわっている人なら必ず一度ならず抱くのではなかろうか。
ひと昔前までならば、女流作曲家といえば、ロベルト・シューマンの妻としてピアニストとして、そして珍しいことに作曲家として活躍したあのクララ・シューマン、「乙女の祈り」の一作のみで知られる夭折の人パダジェフスカ、そして20世紀フランスのいわゆる「六人組」(*)の一人のタイユフェールの名前が思い浮かぶというのがせいぜいではなかったろうか。
しかし、最近、女流作曲家の作品を紹介するレコードも少なからず発表されていて、私たちは有名なメンデルスゾーンの姉にあたるファニー・メンデルスゾーンや、17世紀の後半ヴェルサイユ宮廷でルイ14世に目をかけられたエリザベト=クロード・ジャケ・ド・ラ・ゲールや、史上女性として初めてオペラを作曲した17世紀初頭のフランチェスカ・カッチーニといった女流たちの作品に接することができるようになった。
*「六人組」―第一次世界大戦後のフランスで、ロマン主義・印象主義に対し、旋律や対位法への復帰を主張した作曲家のグループ。ミヨー、オネゲル、オーリック、プーランク、デュレ、タイユフェール。
鍵盤楽器の発達とともに登場しはじめた女流演奏家
しかしながら、星の数ほどいる音楽史上の作曲家の中から、女性の作曲家をひろいあげることはやさしくない、というよりは至難の業に近い。それは、女流作曲家の絶対量が女性の演奏家に比べて極端に少ないということである。例えば女性の歌い手の存在は、オペラの誕生以来、カストラート(*)という特殊な例は別として、どうしても欠くことのできないものであったし、その事情は現在もなお全く変わるところではない。
またピアノの前身楽器であるチェンバロやヴァージナルが、ルネサンス期の発生このかた女性の愛用するサロンの楽器であったことは、数々の名画に見られるとおりである。―読者の中でチェンバロやクラヴィコードを男性が弾いている構図を見た方がいるでしょうか―。
当時の鍵盤が現在のピアノと反対に黒い色にぬられていて、ピアノの黒鍵にあたる鍵盤が白かったのも、女性の白魚のような指が美しく映えるためであったというのは、うがちすぎているとはいえまい。
つまり鍵盤楽器の発達とともに、女性の鍵盤奏者は必然的に輩出されていたのである。
*カストラート―成人しても少年のような高い声を出すために去勢された歌手。16~8世紀にイタリアで行われた。
“女流”という冠をつけて呼ばれる理由はどこに?
そうした女性奏者がプロフェッショナルな存在としての“女流”としての活躍のための開かれた場を得ることができたのは、19世紀以降のことではある。しかし現代において欧米、日本を問わず、女流ピアニストの活躍のめざましさはもう改めていうまでもない。
日本のある高名なピアニストが、“女流”という冠をつけて呼ばれるのを嫌って、単に“ピアニスト”と呼んでほしいという発言をしたことがある。
たしかにアルゲリッチは一頭地を抜く“女流ピアニスト”ではなくして天下一品の“ピアニスト”であるにちがいない。
このように“女流”という語にこだわるのも、この語に性別を明示する以外に、やや差別的なニュアンスがあるからではないか。
それというのも“女流”が、女性としてやはり特別な珍しい存在であるという場合に使われる傾向があると思われる。それが証拠に、まず女性奏者が大半を占めるハーピストのことを、女流ハープ奏者といちいち断わらないではないか。
作曲は女性には適さない?―ハンスリックの説
ところで作曲家の女性の数が、歴史の上でも、他のジャンル、例えばピアニストやヴァイオリニストの活況と比べるならば現在もなお、決して多くないということは―女流作曲家という名がなお健在である理由にもなるわけだが―何を意味するのだろうか。このことに思いをめぐらせるとき思い出されるのが、クララ・シューマンと同時代の評論家・作曲家のハンスリック(1825-1904)の発言である。
彼は『音楽美論』という著書の中で、女性は感情の側面では男性よりも優れているのに、「作曲においては何も成果をみせていない」のはなぜか、と問いかけ、次のように絵解きをする。
作曲には「彫塑的モメント」が必要であるが、それは造形芸術と同じように主観性の放棄を要求する。つまり感情の強いことが作曲の決定的要件にはならないのである。そして女流作曲家が世に「まったく欠けている」一方で、女流作家や女流画家が多く存在しているのもこの理由によっているというのである。(渡辺護訳『音楽美論』岩波文庫112ページ参照)
ハンスリックはシューマン夫妻のよき理解者で、ピアニスト・クララにも筆をすすめている人物なのに、この発言をみた限り、女流作曲家クララを無視していたのかと憤慨したくなる。
しかし音楽史上、最も著名な作曲家クララ・シューマンも、その名声のよってきたるところはピアニストであったことはまずまちがいない。
28歳のクララが、自分の作品(ピアノ三重奏曲)と夫ロベルト・シューマンの『ピアノ三重奏曲 ニ短調 作品63』を比べると自分の曲のほうが柔弱で感傷的に響くと述懐した時、クララはこの世紀の天才と共存することの天国と地獄をみたはずである。
クララの50年以上におよぶ華々しいピアニスト活動に比べると、作品表の作品番号つきの23曲、番号なしのおよそ20曲という数は多いとはいえない。
『女性作曲家のエンシクロペディア』
また、19世紀末から20世紀に活躍したアメリカの女流作曲家H・H・A・ビーチは、ピアニストとして名を馳せていたが、結婚後に夫の反対で演奏活動を断念して、作曲に転向したのであった。また同じくアメリカの現代の女流作曲家キャリー・ウィリアム・クロックマンは、千曲以上の作品を書いているが、社会の要請に合わせるために何人ものちがった男性名を偽って作品を発表したという。
このようなエピソードをかいまみると、二千年以上つちかわれてきた男性主権の西洋社会の中で、女性が与えられてきた「第二の性」という位置と、女流作曲家の姿は無関係ではありえないという実感が湧いてくる。
しかしここでの主題は女性の地位の社会学的考察ではなく、歴史の中で女性作曲家がどのような軌跡を残したのか、その跡をたずねることである。女流作曲家はまたピアニストであった場合もきわめて多い。ピアニストの系譜もまた私たちの対象となる。
幸いなことに『女性作曲家の国際エンシクロペディア』(1981年 ボーカー社 597ページ)という、70の国の五千人の女流作曲家を網羅した女性作曲家の紳士録(ならぬ淑女録?)が刊行されている。これが水先案内人となるだろう。
この他の月刊「ショパン」過去掲載記事はこちらから










