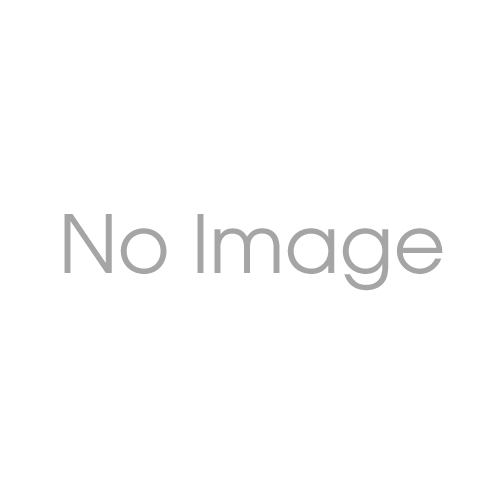昭和59年(1984年)1月1日発行「ショパン」創刊号より転載
ピアノ教育・明日へのベクトルを求めて
「小さなピアニスト」に背伸びをさせないで
大村典子さん
ピアノ教師の方たちには、大村典子さんの名をご存知の方も多いだろう。1980年から始まったそのピアノ教師のための公開セミナーは、83年暮れで通算250回を迎えた。沖縄から稚内まで全国を回りながら、この間大村さんが出逢ったピアノ教師はざっと三万人にのぼる。
もちろん公開セミナー、公開レッスンはめずらしいものではない。が、大村さんのように2年5カ月で250回行うというケースは、全国でも例を見ないものであろう。これほどまでに多くのピアノ教師に耳を傾けられている大村さんのセミナーの魅力はいったい何なのだろう。
セミナーの終わりはいつも“出逢い”の始まり
「一口で言えば、私のセミナーが同じピアノの先生方にとって、身近で日常的であったということじゃないかしら」と大村さんは言う。
「みなさん、ピアノ教師としてどうあるべきかという理想は今までに何度も聞いてきている。でも、今必要なのは、ピアノに心を閉ざしている子どもに、どうしたらピアノの楽しさ、すばらしさを気づかせてあげられるかということでしょう。バッハ、ベートーヴェンをどう教えるかということの前にね」
大村さんのセミナーはいわゆる“講演”ではない。壇上から聞こえてくるのは、大村さんの日常のレッスンである。生徒のピアノ演奏であり、生の声であり、あるいは作文の朗読であり、先生との会話である。
「だから、はじめは、こんなに反響がくるとはとても予想していなかったの」と大村さん。
このセミナーが同じピアノ教師たちにとって、うれしくもあり、またショックでもあるのは、多分にレッスンのテープから生徒たちの表情がはっきりと読みとれるためであろう。ボソボソとうつ向きかげんにしゃべっていた男の子が、ある時、快活に「あの曲、やりたい」と言うようになる。また、ノッペラボウに鍵盤を叩くことしか知らなかった子が、心躍らせ、全身にリズムを満ちあふれさせながら小品をきれいに弾くようになる。あるいは、長いスランプから立ち直り、はじめて音楽へのいとおしさを身をもって知った少女が再出発の意をこめて歌う“贈る言葉”。どの場合もその子なりの成長の軌跡が、声となって、音となって、あざやかに伝わってくるからだ。
驚き、笑い、涙、感嘆をともなって、二時間半のセミナーはあっという間に終わる。そして終わったとたん、大村さんを囲んで、大勢の先生の輪が生まれる。一回のセミナーを聞いただけで、どうしてこのようにたくさんの人の心がうちとけるのだろう。あるいはなぜ、ここから親しい友だちづきあいが始まるのだろう。交友録ノートを回しながら、いろんな雑談が飛び交い、一方では再会を約束している先生方も多い。
どうやら大村さんにとっては、一回毎のセミナーの終わった時点が新しい出逢いの生まれるスタートラインとなっているようだ。
“背伸び”よりも“フィードバック”
今、ピアノを始める子どもたちは、たいてい4~6歳である。そして約5~6年後にはその九割がピアノをやめてしまうという。
「だから、ピアノのレッスンをやっている期間って、ホントに短いのね。つまりこの数年間の習い方が勝負。レッスンをやめても一人歩きできるような基礎力を、短期間に身につけなければね」と大村さんは言う。
「私の場合、ソナチネをやっている子どもでも“これは”と思ったら易しい教材にまで戻す。そこの決断が生死を決めるんです。そして、徹底的に弾けるまでくり返す。そうすると、はじめ1巻1冊に3ヶ月かかったものが、2回目には3週間、3回目には10日間でできるようになる。やさしい曲を数たくさん弾かせることで、子どもは“こんなに楽々と弾けるようになった”と確実に自信をつけるから」
ツェルニー第一過程の40番くらいまでを2度目には1ヶ月で弾き終えた子が「先生、ボクは昔、ここまで5ヶ月もかかっちゃったんだネ」と驚くそうだ。“背のび”よりも“フィードバック”なのである。イヤイヤさせるのではなく、どんどん弾けるものをふやすこと。必要なことは、出してしまった“音”を責めるのではなく「その“音”をこう伸ばせばいいんじゃない?」と常に一段上への方向づけを行うことである。
大村さんは言う。「子どもの“練習ぎらい”の最大の原因は、まず音符が読めないことだと思うのね。音符を一人で読めるようになれば、自分から積極的にピアノに向かい出しますよ。私は“入門式”で必ずかんたんな曲を初見で弾かせてみる。初見をやらせれば、現在その子の持っている音楽力をその場で見抜くことができるから」。
読譜を集中的にやりつつ、かんたんな曲を短期間にたくさん弾かせることで、子どもはいつのまにか、読譜に関して何の苦痛も感じなくなる。だから、パッとあるページを開けば、すぐ弾き出せる。音符の並び方や曲の仕組みが頭に入って、ひとつのフレーズを一気に読みとる力ができるのだ。
「音楽のボキャブラリーがふえるわけですね。その結果、伴奏もすぐつけられるようになるし、バリエーションなどのアレンジ力、応用力にも発展する」。
むしろ長い期間かけて100点をねらうよりも短期間で80点をたくさんとれるように。多くのピアノ教師が経験していることだが、昔1年かかってたった2曲をやりとげたり、音大の4年間で大曲を数曲やっとこなしたというやり方では、今の子どもには全く通用しないのだ。
「楽しんだという実感なしに、次の曲にやっと進ませても、とたんに青息吐息。絶対、伸びないのです。子どもは自分自身に余裕が生まれた時に、はじめてグンと伸びるものだから」。
心の“歌”を表現できる「大村教室」のピアニスト
「でも、日常、どんどん弾けるものと並行させて、発表会のように目標を立てて、ある程度高いものに挑戦させるという意識をつけるのも必要。だから、発表会の選曲もいろいろと凝るわけですが、基本的には、子どもが完全に自分の力で弾き切れるものを選びます」
大村教室の発表会は不思議といえば不思議だ。第一、アガル子がいない。そして、ふだん着でステージに現れるのだが、気軽にサッとピアノに向かい、堂々と弾き始める。そして音が鳴り始めると、「えっ、あんな小ちゃな子が?」とだれもが我が耳を疑うほどの演奏なのだ。
たとえば、全身からあふれるリズム感、自然なフレージングとアーティキュレーション、ハーモニーの変化と色彩を浮き出たせる微妙なペダリング、そしてテンポ・ルバートやアゴーギクのセンスに至っては、実に大人顔負けなぐらいである。
確かにメカニカルにバリバリ弾ける子どもたちではないかもしれない。しかし、どんな簡単な小品にしても、聴く者の耳を魅きつける“歌”がそこにあるのだ。小さいけれども完璧に「一人前のピアニスト」である。「聴いている人は楽譜を見て聴いているわけではないでしょ。出てくる音を聴いているんだから。発表会でいくら大曲をやっても、トロトロ弾いたら、絶対上手に聞こえませんよね」。
その年齢に応じた最高の段階、最高の音楽性に目標を合わせる。この大村さんのやり方は、もはや相手を“子ども”としてではなく、完全な“大人”として向き合う姿勢なくしては成り立たない。日ごろからの、「あげ底」でない「背伸び」させない育て方から生まれるものだろう。
しかし子どもたちは言うそうだ。「先生、でもねェ、ボクたちの楽譜、はずかしくて人に見せられないよね、簡単だモン!」確かに一見したところ、譜割としては混み入っていない。
「教師はまず弾いてあげなければ。簡単な曲でいいんです。ブルグミューラーを初見で、しかも情感こめてきれいに弾いてあげて下さい。それが子どもの心に染みわたったときには、自分の方から“その曲やりたい!”って言いますよ」
ふっきれた時一人歩き始める生徒たち
発表会もいよいよ終わりにさしかかった時、大村さんが最後のあいさつを始めると、ステージに残っている生徒がいつのまにか、バックでピアノソロを奏で始めたり、自然にアンサンブルを流し始めたりする。静かに“イエスタデイ”や“グルダのアリア”が聞こえてくると会場は温かいムードに包まれる。それは、先生に感謝の意を込めた生徒代表の“即興”なのだ。このような、先生と生徒の音楽のふれあいに、会場のだれもが、うらやましさを感じてしまう。
七年前、入門時にはブルグミューラーさえおぼつかなかったのに、自分の意志と力で音楽を続け、83年春には見事、東京芸大(楽理科)への道を手に入れた女の子のように、あるいは、ロックバンドのキーボードプレイヤーとして腕をあげ、北海道大学に通うかたわら、ヤマハのインストラクターを務める男子生徒のように、大村教室を巣立って一人歩きし始める生徒が次々と生まれてくる。
その生徒たちに共通して見られるのは、ある種の「ふっきれ」つまり自由かっ達さと音楽を楽しむ姿だ。一人一人が自分の音楽の世界を持ちつつ、アンサンブルや発表会などの体験を通じて音楽の楽しさを発見してゆく。
種蒔く時期から育てる時期へ
大村さんは、ピアノ教育の“原点”を、生徒に音楽を教えることではなく、生徒の心から音楽を引き出すことと考えている。「たまたま私のやり方は、子どもによくしゃべらせ、よく書かせ、よく弾かせ、というところから始まったけれど、先生方一人一人にはそれぞれご自分の得意分野があるはず。それをどんどん毎日の指導に取り入れていってほしいと思います。でも、最近なかなかアイディアが豊かな先生、ふえてますねェ」。
250回のセミナーを通して、3万人のピアノの先生方と出逢った大村さんは、多くの人に刺激を与えつつ、同時に相手からもできる限りのものを吸収しているらしい。この4年間の成果は、現在七巻にまでなった「交友録」に結集されている。それを見ると、大村さんの“人間好き”の一面がよくわかる。
生徒が言うそうだ。「先生、このごろイキイキしているネ」と。多くの人との交流が、大村さんにより新たなエネルギーを注ぎこんだのか。
現在のピアノ教師に、欠けている横のつながり、仲間同士の情報交換といった機会を少しでも多く作りたいと大村さんは願っている。「私はこの約4年間、あちこちに種を蒔いてきた。でも、蒔きっぱなしじゃダメなの。同じ悩みを抱えている先生同士、今や北も南もないんです。全国的に交流できるネットワークに拡がるようにまずその根を育てていきたいと思うんです」。
ピアノ教師のためのセミナーは、当分続きそうだが、「この4年間の足跡をふり返ってしっかりと地固めをしなくちゃ」と語る大村さんである。
大村典子さんのプロフィール
国立音楽大学大学院楽理科修了。ヴィヴァルディ研究家として国際的に有名。1978年にイタリアで刊行された「ヴィヴァルディ生誕300年記念論文集」に世界の11人の学者の1人として寄稿している。1980年から東京ヴィヴァルディ合奏団の“ファミリーコンサート”の企画構成と解説を担当。ピアノ教師歴は16年。1979年から『ピアノの本』(草思社刊)に連載執筆。ピアノ教育の問題点をいろいろな角度からとらえ大きな反響を呼ぶ。1980年から全国各地でピアノセミナーの講師をつとめる。著書にベストセラーとなった『ヤル気を引き出すピアノのレッスン』(音楽之友社)『ピアノが好きになる教え方、習わせ方』(草思社)など。また『別冊・太陽“ピアノ気分”』(平凡社)や『ミセス』(文化出版局)でも大村教室が紹介され、「大村式レッスン法はピアノに限らず全ての教育に共通するもの」と、小学校のPTAからの講演依頼も増えている。