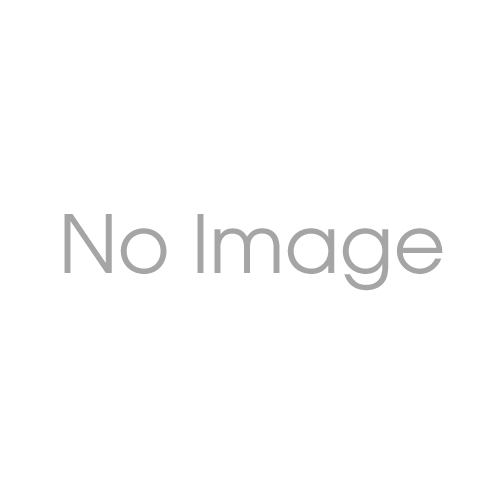
≪音楽にめざめた刻……≫
私のベートーヴェン・ピアノ・ソナタ
―ロロフ先生とケンプの演奏に導かれて―ピアニスト、洗足学園大学ピアノ科教授 山根弥生子
ロロフ先生の貴重な助言
私がピアノの道にどうしても入りたくなった直接の動機は、戦後まもなく来日されたラザール・レヴィ先生の演奏に触発されたのが原因といえる。その演奏に心を動かされたベートーヴェンのソナタのうちの2曲が、何年か後に私が日本でデビューする時のプログラムに入ってしまったことも、いま考えると偶然の一致というよりは意味が深いように思う。
フランス人でありながら、レヴィ先生のベートーヴェンへの傾倒は並々ならぬものであったし、生徒は勉強の基礎として、いろいろのベートーヴェンのソナタを次々と課せられた。そしてそれと並行したのが、ショパンという課題であった。荒っぽい云い方をあえてすれば、この両方をこなすことでピアノの勉強の骨子は成立するといえる。
コンセルヴァトアール在学中の頃の私はショパンは苦手だったが、ベートーヴェンには一種の安心感をいだいて接していた。上手な仲間が多くて太刀打ちできそうになくても、課題がベートーヴェンやバッハなどになってくると、試験もそう心配でなくなった。
いま考えればその頃の私は全く弾けない生徒だったのだが、音楽的にはなにがしかの特徴があるということで試験官の先生がたの同感を得て卒業ということになったのではないか、と思う。世間的にはかなり早々と卒業できたという幸せな状態にもかかわらず、私自身は心細くて困っていた。はっきりいって、全く一人前になれないうちにクラスに居られなくなることに途方にくれた。
馬鹿だった私は、その頃は、指がまわり大きな音が出て弾きにくいパッサージュがらくらく弾けるというような外面的な、いわゆる技巧が発達しきれば音楽的表現もそれにつれて自然にうまくなってくれるのか、と思っていた。
これは全く逆で、表現したいことを実現するためには頭が指に命令を下すのが順序だという当り前のことがやっと当り前に身についてきたのは、チューリッヒでエガー先生と、その後ベルリンでのロロフ先生のご指導のおかげであった。
とくにロロフ先生には、数々のドイツ音楽の表現の貴重なパターンを教えていただいた。ベートーヴェン、シューマン、ブラームスなどの演奏にロロフ先生の助言がなかったら、私はまだ長いこと低迷を続けていたかも知れない。
このパターンをもとにして、今までモヤモヤしていた表現ということが具体的にはどういう形で作られてゆくことになるのか、そのプロセスが私にもはっきりつかめる糸口がつかめたのだった。
他のことにはひどく性急な私が、ことピアノに関してはばかに忍耐強くなった。自分に云いたいことがあるならば、それを何とか表現してみるためにどんな簡単な一句でも時間をかけてゆっくり納得ゆくまでやってみることに興が乗ってくると、云いしれぬ満足感につつまれる。
演奏家って幸せだなと思うのは、こういう時と、さらにもっと幸せなのは聴衆が演奏に聴き入ってくれている時、おたがいの気持が通じたのが伝わってくる時である。聴衆なしに私たちの進歩は考えられない。勉強を重ねたあげくにその後の精神の飛躍のために、聴き手の同感を抜きにしては考えられないのだ。その意味では聴衆は神様といいたくなる。そして舞台を重ねるごとに、謙虚な気持になってくる。
ケンプの全曲演奏を聴いて
デビューした頃の私は、公の席で弾けるベートーヴェンはほんの何曲もなかった。おまけにそれらはいわゆる有名でないソナタばっかりだったが、必要にせまられて次々にいろいろの曲と取り組んでいるうちに病みつきとなり、遂に、どうしても全32曲を演奏してみたくなった。ちょうど1970年が生誕200年、また77年が没後150年という外的条件が目の前に二回もあったことは、計画を実現する上でたいへん幸せなことだった。
ひとくちに全32曲といっても、実際にこれらをとどこおりなく弾き通せる大変さは、やってみないと実感できないのは本当だと思う。弾く方も大仕事である。
実をいえば、生の演奏で32曲全部を通し聴いたのは、私は70年にケンプが東京で弾いたのしか経験していない。
前から尊敬していたケンプだったが、この時の感激は忘れられない。春先の肌寒い日もまだ多かった頃であったが、文化会館の冷えびえした大ホールで、さり気なく始まり、だんだんと熱気を帯びてくる彼の演奏を私は全精神で受けとめたい思いで聴いた。
自分で全曲を勉強していた最中だからこそ、聴く立場でも一句一句が他人事でなく関心をひく。おこがましいながらまるで自分が半分ケンプになって、演奏している彼の気持の動きまでわかるような気がし、聴き終るとがっくりと疲れた。
最終回が終って、感激のあまり楽屋までたずねてゆき、びっくりするケンプに「すばらしい演奏に心打たれてあえてうかがったのですが、まさか教えてはいただけませんでしょうね?」とおそるおそるおうかがいをたててみた。するとケンプは、
「私は人を教えないが、夏にイタリアで公開レッスンをやっている。そこではベートーヴェンのソナタをやっているけれど、そこで弾くには相当の数のソナタをこなしていないと出る資格がないのだが……」
と、まるで私をうら若い音楽学生かと思われたように云われたので(私自身は内心若く見えたらしいことにまんざらでもなかった)、「じつは全部手がけました」と答えたが、彼にはどうやら信じられない様子だった。それでも住所つきの名刺をくれたのは、私がそう怪しく見えないですんだということであろう。
夏には考えたがイタリアには行かなかった。すばらしい生演奏の感激をバネに一人で勉強して、夏休みには夏休みで充分海で遊び、秋の連続演奏会にそなえるのが良いと判断したからだ。事実その年の前半は、ずいぶん何回もいろいろの組み合せでソナタの演奏をあちこちでやって曲をあたためていたから、夏には休むことが必要だった。
9月終り頃から12月のベートーヴェンの誕生日までに、全曲を8回にわけ、作曲年代順に演奏した。これが70年の時で、77年にもやはり前回と同じかたちで、時期も同じ頃にやった。二回目は責任がもっとまして、一回目よりももっとこわかった。ただホールの音響条件は二回目のほうがずっと有利だったし、たぶん演奏にも七年の月日がなにがしかのプラスをあたえてくれたと思う。
それぞれの曲についての実感
若い時代に私は、ソナタの中でもとくに後期のソナタに一番ひかれていた。後のものほど良いというくらいに。それは今だってOp.111の二楽章の主題を聴くと涙が出るくらい感激するのだが、それと同時に、初期のソナタの瑞々しい美しさに大きな魅力を感じないではいられない。
Op.2の1の出だしからしてベートーヴェンが作品番号をつけた最初のソナタにふさわしい堂々たる個性が表われているのに、この辺のソナタはまだハイドンの影響下うんぬんなどと解説に云われたりしては、ベートーヴェンの代りに怒りたくもなる。
Op.2の2の二楽章も私のたまらなく好きなところ。Op.10の1も2も明暗の色あいは正反対だが、それぞれすばらしい。
Op.10の1の終楽章に「運命」のモティフが見えがくれしている。耳の病気の予感だろうか。Op.10の3は、次のOp.13におとらずむしろこちらの方が四楽章で大ソナタと云えないかなと思ってしまう。もちろんOp.13のハ短調の悲劇的な内容の重々しさから大の字にふさわしいのかもしれないが。
幻想風のソナタの時期に入るOp.26は私にはとても弾きにくい曲に思える。全曲を通じてソナタ形式の楽章が一つもないということがその理由ではないはずだが、もしかすると葬送曲があるということに悲しさを感じて弾きたくないような感じにおそわれるのかもしれない。
Op.27の2曲、Op.28からOp.31の3曲(この31の1の終楽章は少しだだっ広いが、シューベルトの長さを考えれば気にならなくなる)もそれぞれ良い曲だし、Op.53や57が傑作中の傑作ということに異論はないのだが、名のついてないソナタも聴いてもらいたい一心から、つい有名ではない曲の方をほめてみたくなる。
Op.81a、Op.90、Op.100などの一種の柔かみの優先する曲には、気持の上でなじむのに私はかなり時間がかかった。
Op.101と106は夢中で勉強した。とくに106は覚悟はしていたがむずかしかった。でも不思議なこの音楽の力にひかれて、何年がかりでも勉強は苦にならなかった。「フーガの入ったソナタ」ときいただけでも好きなパターンでわくわくした。
Op.110と111も両方ともすばらしい。とくに111を弾き終ると、ベートーヴェンがここで彼のソナタの全32曲の長い過程に云うべきことを全部云いつくしてくれたという実感が伝わってくる。
ソナタの芸術のすべてが完結した、というような充実と満足と安らぎさえただよって、弾く者の心を感動につつみこむのだ。
この他の月刊「ショパン」過去掲載記事はこちらから










