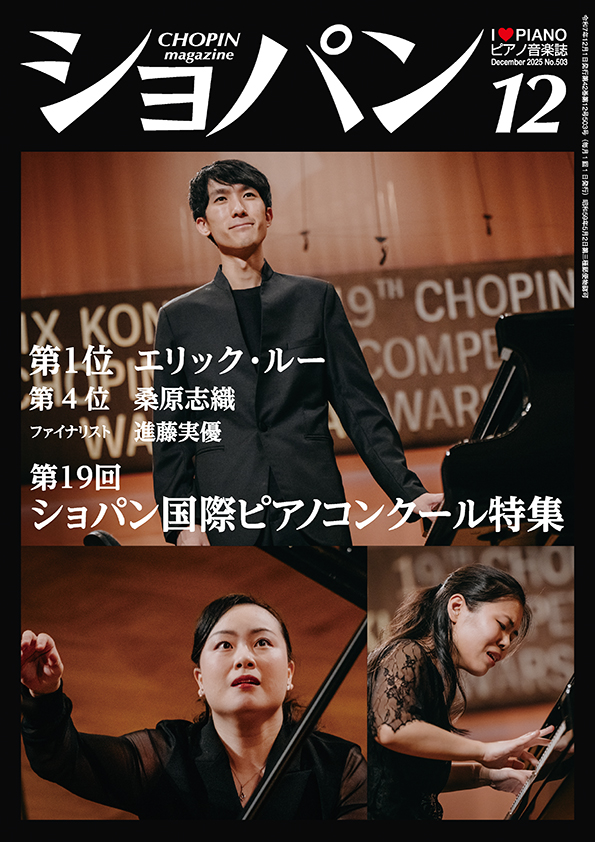編集部伊藤の珍部黙示録第10回 東京家政学院中学・高等学校 俳句同好会「全国準優勝に輝いた俳句ガールたちの夏」
こんにちは? 編集部の伊藤です。今回で珍部黙示録も第10回を数えましたね〜。おめでとうございます?これからもますます頑張っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 さて、今回の節目となる珍部黙示録は、その道の実力校をご紹介します。今回のテーマは「俳句」。ご紹介するのは、今年愛媛県で行われた高校俳句部の全国大会「俳句甲子園」で、準優勝を果たした東京家政学院中学高等学校の俳句同好会です。俳句のルールを覚えよう
部活紹介の前に、俳句のルールを簡単に勉強しましょう? まずはじめはこの2つ。 ① 五・七・五 これはみなさん知っていますかね。俳句は五・七・五のリズムで詠みます 例)閑(しず)かさや 岩にしみ入る 蝉(せみ)の声 誰に教わったわけでもないのですが、このリズム、なんだかとっても心地よく感じますよね。これが俳句の基本となる、五・七・五のリズムです。 ②季語を入れる また、季語という季節を表す言葉を使うことも俳句の醍醐味のひとつでもあります。 春・・・桜、入学式、雪解け など 夏・・・花火、浴衣、ひまわり など 秋・・・紅葉、ハロウィン、お月見 など 冬・・・雪、クリスマス、バレンタイン など もちろん上記の言葉以外にもたくさんの季語があります。そのような季語を必ず入れることが、俳句のルールのひとつとなります(※ちなみに、この季語を入れない五・七・五の句を「川柳(せんりゅう)」と言います) とりあえずはこの①と②の2つを覚えれば、もう誰でも俳句が詠めちゃいます。 けれども俳句の世界はとっても奥が深い世界。そんな俳句の世界を、部員のみなさんのインタビューと共にご紹介しようと思います。俳句との出会い、そして挫折からのスタート
俳句との出会いはメンバーが中学3年生の冬、今から3年前にさかのぼります。 「当時図書委員会でお世話になっていた児島先生(現俳句同好会顧問)の、『俳句甲子園というものがあるんだけどでてみないか?』という一言がきっかけでスタートしました。最初はなんとなく始めたはずなんですが、気付けば高3の最後まで続けていましたね笑」 そう話してくれたのは、同好会結成時からのメンバーの大西さん。 「はじめたばかりの頃は季語とか全然わからなかったのですが、先生が『とりあえず自由に詠んでみなさい』ということで、とにかくやってみようと。今考えるとその頃の句は、本当に支離滅裂なものばかりだったのですが......笑」 大西さんだけではなく、みなさんはじめは本当に手探りで俳句を覚えていったとのこと。それでもいろいろと詠んでいくうちに俳句の呼吸などをつかんでいきました。 そして迎えた初めての大会。そこで彼女たちは「俳句甲子園」のレベルを目の当たりにします。 「高校1年生の時、わたしたちがはじめて俳句甲子園に出場した時は、地区予選の段階で負けてしまいました。そこからの1年は楽しさよりも、『どうやったら全国大会に行けるんだろう』という不安のほうが大きかったような気がします。けれども、『全国大会に必ず出る』という目標に負けずに向き合えたことがその後の全国大会出場に繋がったんだと思います」と部員のみなさん。 顧問の児島先生もこう話します。 「あの負けをきっかけとして、生徒たちのほうから『俳句をもっとやりたい』と言ってきたので。この瞬間『あ、次の大会は(全国に)行けるな』と感じましたね」 「全国大会に必ず出る」という目標に対し生徒自身の自主性で取り組めたこと、そして負けを糧にする精神力の強さが、その後の高校2年時の全国大会出場につながっていきます。最後の夏、最後の俳句甲子園
 高校2年の大会では全国大会に出場したものの予選で惜しくも敗れてしまいますが、迎えた高校3年時最後の夏。家政学院俳句同好会は昨年度を上回る成績で本戦出場まで駒を進めます。 そして準決勝、相手は強豪・開成高校のBチーム。 俳句甲子園では、5人1チームで対戦し、事前に準備した句を両チームから1人ずつ順に披露しあい、審査員の得点をより多く勝ち取ったほうにポイントが与えられます。準決勝はもつれにもつれ、2-2の同点での最終局に。ここで披露した家政学院の句が会場にどよめきを与えます。 「利口な睾丸(こうがん)を揺さぶれど桜桃忌(おうとうき)」 エリート男性を揶揄したとされるこの一句。これが審査員の方々よりたいへんな好評を得ます。 「自由でアナーキーな表現が俳句でできることを教えてもらった」 「はじめは乱暴な句だと思ったが、男性の隠喩など読みを展開すると豊かさが広がる」 という審査員からのコメントが。 この一句について部員のみなさんは、 「家政学院の俳句スタイルは、『自由な句を作ろう』というところにあります。よく『女子高生が過激な言葉を使ったから』とか言われるんですけど、本当はそうじゃない。一句を生み出すには本当に自分自身との戦い、自分と向き合うことの繰り返しなので、苦しさだってあります。そういった中から生まれてきた句。インパクトだけではなくて『なぜあの子たちがこんな句を詠んだんだろう』というところまで考えていただければ、本当のおもしろさが見えてくると思います」と言います。
高校2年の大会では全国大会に出場したものの予選で惜しくも敗れてしまいますが、迎えた高校3年時最後の夏。家政学院俳句同好会は昨年度を上回る成績で本戦出場まで駒を進めます。 そして準決勝、相手は強豪・開成高校のBチーム。 俳句甲子園では、5人1チームで対戦し、事前に準備した句を両チームから1人ずつ順に披露しあい、審査員の得点をより多く勝ち取ったほうにポイントが与えられます。準決勝はもつれにもつれ、2-2の同点での最終局に。ここで披露した家政学院の句が会場にどよめきを与えます。 「利口な睾丸(こうがん)を揺さぶれど桜桃忌(おうとうき)」 エリート男性を揶揄したとされるこの一句。これが審査員の方々よりたいへんな好評を得ます。 「自由でアナーキーな表現が俳句でできることを教えてもらった」 「はじめは乱暴な句だと思ったが、男性の隠喩など読みを展開すると豊かさが広がる」 という審査員からのコメントが。 この一句について部員のみなさんは、 「家政学院の俳句スタイルは、『自由な句を作ろう』というところにあります。よく『女子高生が過激な言葉を使ったから』とか言われるんですけど、本当はそうじゃない。一句を生み出すには本当に自分自身との戦い、自分と向き合うことの繰り返しなので、苦しさだってあります。そういった中から生まれてきた句。インパクトだけではなくて『なぜあの子たちがこんな句を詠んだんだろう』というところまで考えていただければ、本当のおもしろさが見えてくると思います」と言います。  判定の末、家政学院にポイントが入り見事強豪開成高校Bに勝利。なんと家政学院俳句同好会結成5年での全国大会決勝の舞台に駒をすすめる快挙を成し遂げます。 その後の決勝の舞台では敗れたものの、最終的に準優勝を勝ち取り、高校最後の大会の幕は閉じました。
判定の末、家政学院にポイントが入り見事強豪開成高校Bに勝利。なんと家政学院俳句同好会結成5年での全国大会決勝の舞台に駒をすすめる快挙を成し遂げます。 その後の決勝の舞台では敗れたものの、最終的に準優勝を勝ち取り、高校最後の大会の幕は閉じました。 
究極の一句と、俳句を通して得たもの
ここまで自由な句を作れる家政学院の俳句同好会。彼女たちが考える究極の一句について質問してみました。 「究極の一句......そういえば先生が前に究極の一句はひとつだけ存在するって言ってましたね!」(部員) 「はい、まだ詠まれていない一句ですね。俳句というのは使える言葉やフレーズも限られているので、限界があるはずなんですよ。すべての俳句は読み尽くされているはずなんだけれども、たったひとつだけもし読まれていない俳句があるとすれば、そのひとつのために俳句を詠むことは価値があるはずだと。それが私の考える究極の一句です」(児島先生) なかなか深いですね〜。その一句のために俳句を作り続けるのだということでした。 では、俳句で得たものというのはなんでしょう?? 「物事を多方面から見ようとする意識がついたと思います。俳句をする上では、句の深さを読み取る力や習慣が必要になってきます。それは、日常生活でも同じで、物事の表面上だけではなくて、その本質だったり、目に見えない良いところだったり。そういったことを見ようとする習慣や意識は俳句を通して身につきました」 また、こんな意見も出てきました。 「俳句甲子園では、作った俳句の短所が気になってしまってギリギリになって変えてしまうこともありました。けど大切なのは短所を見ることではなくて、その句の良いところ、本当に深い部分で俳句を見つめてあげることが大事なのではないかと気付きました」 それって、本当に大事なことですよね。これってまさに自分自身に置き換えても同じじゃないですか? 人間生きていると自分の短所が気になってしまって自信をなくしてしまうような時もあります。でもそうじゃない。自分の長所を見つけ、伸ばしていく。俳句と向き合うことは自分と向き合うことだと部員のみなさんも言います。 このインタビューを通し、彼女たちが俳句から得た大きさを痛感せざるを得ない筆者でした。やはり何かに一生懸命打ち込むということは、本当に大きなものを得ることができますね。その裏には、苦しさだったり、壁にぶち当たったりと、すべてがうまくいくということではなかったはずです。けれど、それを乗り越えた人が得た経験と豊かさは、今後の人生において必ず糧になっていくのだと思います。 彼女たちが俳句に捧げた夏は終わりました。今後は大学受験など、高校3年生の彼女たちの新しいチャレンジが始まります。新しいステージで壁にぶち当たった時、自分自身に迷いが生じる時もあるかと思いますが、俳句で得た経験を思い出し、大きく羽ばたいてくれることを願います! (文・取材●伊藤文人)
(文・取材●伊藤文人)