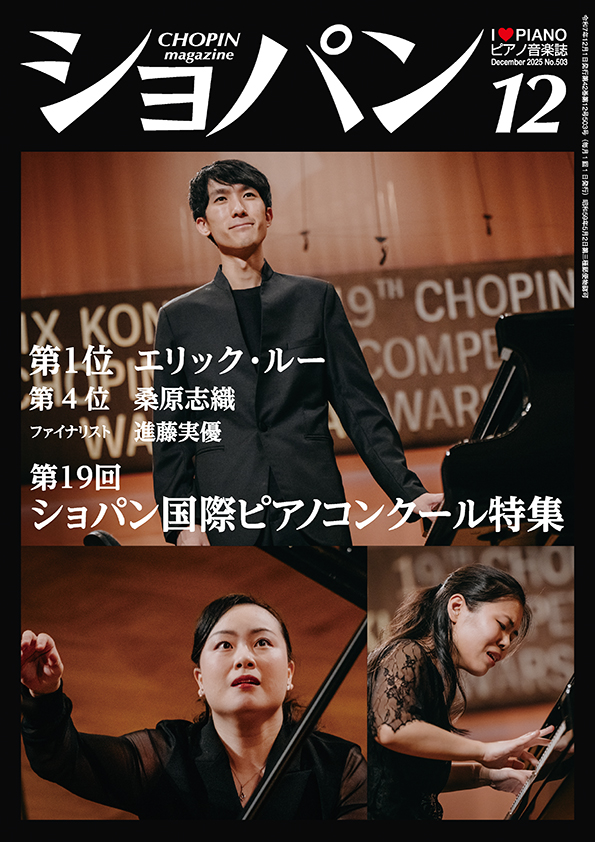詳解オペラ名作217もくじはこちら
詳解 オペラ名作217 野崎正俊 より
ドイツオペラ
W. A. Mozart, Der Schauspieldirektor 1786
劇場支配人[1幕]モーツァルト作曲
❖登場人物❖
ヘルツ夫人(S) ジルバークラング嬢(S) フォーゲルザング(T) ブッフ(B)
以下は台詞のみの俳優 フランク アイラー氏 ヘルツ氏 マダム・プファイル マダム・クローネ マダム・フォーゲルザング
❖概説❖
モーツァルトは1782年に完成した「後宮からの逃走」において、ジングシュピールのスタイルを完成させた。この作品も、ドイツ語の台詞が音楽でつながれるという意味ではジングシュピールの形態に近いが、それ以上に芝居に音楽が付け足されたという性格が強い。というのも、この作品は全十場からなり、その中で演奏される音楽はわずかに四曲にすぎないからである。小規模なドラマには不釣合いなほど立派な序曲が置かれているのがユニークである。いずれにしても、これは歌劇というよりも音楽劇といったほうが正しく、ドラマの部分を省いて音楽部分だけが演奏されたり録音されたりすることも多い。モーツァルト自身は〈一幕の音楽つき喜劇〉という副題をつけている。
「フィガロの結婚」を作曲中に書かれているだけに、音楽的にきわめて充実した内容を持つ作品である。音楽部分で登場する人物は四人である。皇帝ヨーゼフ二世の義兄弟にあたるオランダのアルベルト・フォン・ザクセン=テーシェン大公夫妻歓迎祝祭に際しての初演では、サリエリの「まずは音楽、つぎが言葉」と併演された。
フランクという名の興行主がザルツブルクで芝居の興行をするための許可を得た。そして自分の劇団を組織しようとしている。そのために団員を募集するが、それを目当てに自薦、他薦の俳優や歌手たちが応募にやって来てオーディションを受けることからはじまる。
まずフランクが、喜劇役者ブッフ(滑稽とか喜劇とかいう意味)と演目や役者について打ち合わせている。はじめは役者のオーディションが行われるが、最初にやって来たのは金持ちの銀行家アイラー氏で、自分がご贔屓(ひいき)の女優マダム・プファイルを使ってくれるよう彼女を推薦する。そこに当のマダム・プファイルが現れて、劇中劇の一部を披露する。
次に売り込みにやって来るのはマダム・クローネである。彼女は続いて現れたヘルツ(ハート、つまり心)氏とともにラシーヌ、コルネイユばりの古典悲劇の一部を演じてみせる。さらにひとかど有名になっている女優マダム・フォーゲルザング(鳥の歌)が現れ、ブッフと劇中劇を演じてみせる。
ここまでが俳優の売り込み場面で、それが終わると今度はオペラ歌手のオーディションがはじまる。トップバッターはヘルツ夫人である。彼女は名前の通り、心のこもった情感豊かな歌を歌う。
第一曲:アリエッタ「別離の時の鐘は鳴り」
別れの鐘が鳴って、酷い別離の時を告げている。私は愛するダモンと別れて、どうやって生きていったらよいのでしょう。霊魂になってでもいつもあなたのお供をしていたいのです。それなのにあなたは永遠に忘れてしまおうと言うのですか。あなたがそんなに不実な人だとは思えません。別離に悩む心はそのような浮気など知りません。運命はすでにあなたの心と固く結びつけられていて、もう切れることはないのです。
次にジルバークラング嬢が現れて、小鳥のように軽やかな声でコロラトゥーラの技巧をちりばめて歌う。
第二曲:ロンド「若いあなた!」
若いあなた! 私は喜んであなたの愛を受け入れます。あなたの優しい眼差しの中に私はいつも喜びを見いだすのです。しかし、でも! 私たちの恋に悩みが伴うような時には、恋の喜びはそれを消してくれるでしょうか? 若いあなた、よく考えてね。あなたの心、あなたの手ほど私にとって大切なものはない。清らかな愛の火に包まれて、私は私の心を担保として差し上げます。
興行主は素晴らしい歌手が二人も応募して来たのを喜ぶが、今度は二人の女性歌手が自分こそプリマ・ドンナだといって互いにトップの座を譲らない。そこに現れた男性歌手フォーゲルザングがなだめに入る。
第三曲:三重唱「私がプリマ・ドンナよ」
まずジルバークラング嬢が「私こそプリマ・ドンナよ」と主張する。最初のうちヘルツ夫人は低姿勢で受け応えするが、やがて「そんな高慢ちきな人は知らないわ」と言い返す。そこにフォーゲルザングが割って入る。彼は、お二人はそれぞれ特長を持っているので優劣争いをするのは意味がない、そして芸術家は謙虚でなければならないと諭す。ジルバークラング嬢は自分の主張を取り下げるので、いったん争いは収まるかにみえるが「それならば私がプリマ・ドンナよ」とヘルツ夫人が言うので、再び主役争いは収拾がつかなくなる。フォーゲルザングは繰り返し「お静かに」と言ってまたもやなだめにかかるが、“ピアノ”“ピアニッシモ”“カランド”“マンカンド”“ディミヌエンド”“デクレシェンド”と、「静かにしろ」を意味する音楽用語をしきりに並べ立てるのが面白い。
そして最後に全員が登場して大団円を迎えるのが第四曲で、ヴォードヴィルの形式をとっている。ヴォードヴィルとは、ひとつの旋律に簡単な和声をつけて軽妙に歌ってゆくコミカルな歌である。
第四曲:ヴォードヴィル「芸術家はだれでも栄光を求めて努力する」
まずジルバークラング嬢が、芸術家は誰でも栄光を求めて努力するもので、第一人者になる志がなければ伸びないという。これに対してヘルツ夫人、フォーゲルザング、ブッフは、芸術家は人より優れるよう努力することが大切だが、他人を軽蔑してはならないと歌う。そしてフォーゲルザングは、個人よりも大勢が調和している方が人に好まれると続ける。ヘルツ夫人が芸術家はおのおの個性を発揮し、芸術と天分を調和させた上で結果はお客の拍手に委ねようと言う。
最後に俳優のブッフが、私の名前にO(オー)をつければブッフォ、つまり喜劇役者になる。歌はダメだが、それでも尊敬されるものだと締めくくる。
Reference Materials
初演
1786年2月7日 シェーンブルン宮のオランジェリー(ウィーン)
台本
ゴットリープ・シュテファニー/ドイツ語
演奏時間
24分(序曲を含む音楽部分のみ、ベーム盤CDによる)
参考CD
●グリスト、オジェー、シュライアー、モル/ベーム指揮/ドレスデン国立管(DG)
●グルベローヴァ、テ・カナワ、ハイルマン、ユングヴィルト/プリッチャード指揮/ウィーン・フィル(D)
●メスプレ、モーザー、ゲッダ、ヒルテ/シェーナー指揮/バイエルン国立管(EMI、台詞入り)
参考DVD
●ザモイスカ、メタクサキ、ベルヒトルト/フックス指揮/ザルツブルク・ユンゲ・フィル(DG)