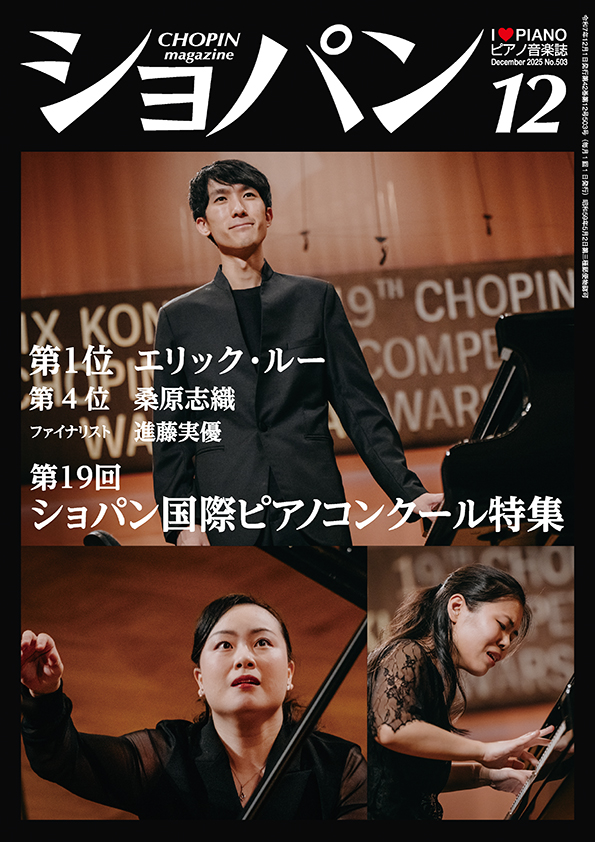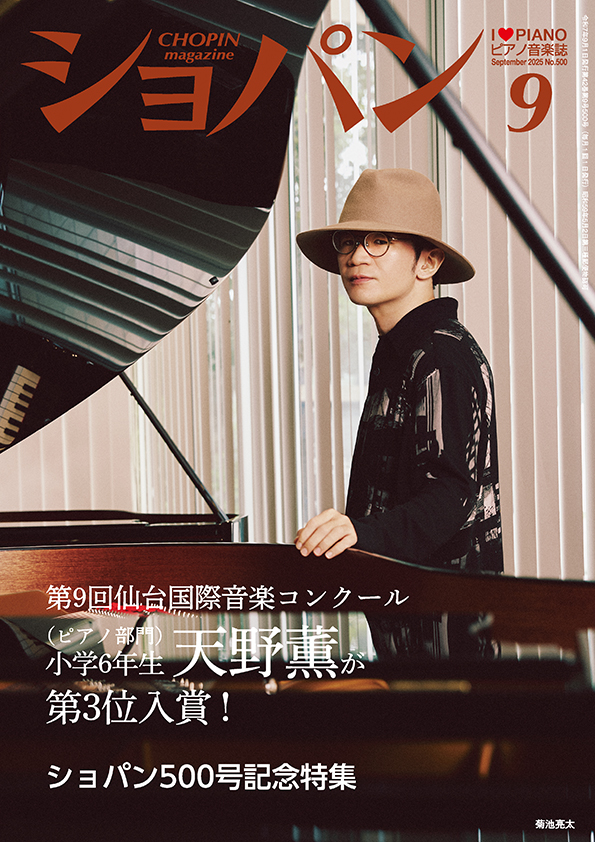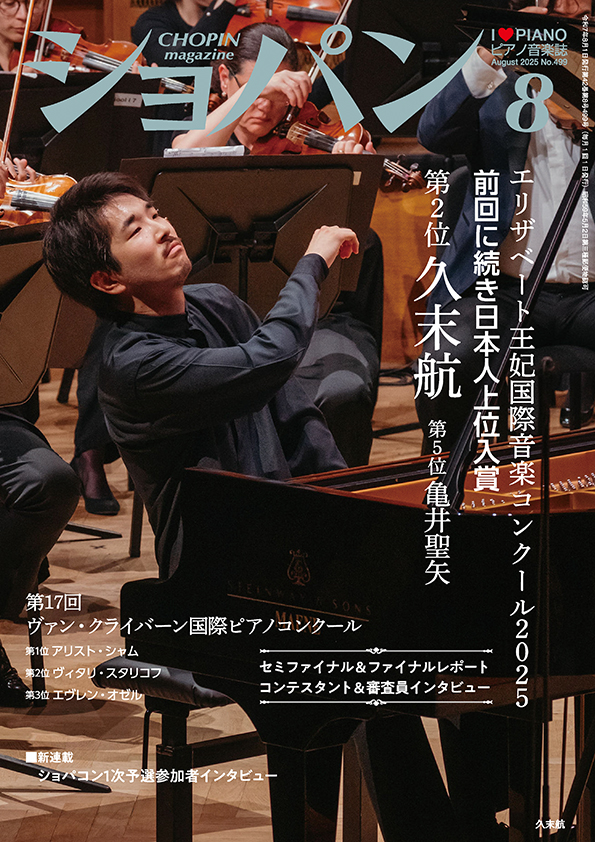詳解 オペラ名作217 野崎正俊 より
コラム
インテルメッツォ
「インテルメッツォ」は、日本語に訳すと間奏曲ということになる。オペラでは幕間にオーケストラだけの演奏による間奏曲が入る例があり、マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」などがその代表的な例であるが、ここでインテルメッツォというのは幕間劇のことである。
十八世紀になってオペラがヨーロッパ 各地に広まると、イタリアのナポリではナポリ派と呼ばれる作曲家によってオペラが書かれるようになった。それはシリアスな題材を扱った格調の高いオペラ・ セリア(正歌劇)と、コミカルなオペラ・ ブッファ(喜歌劇)という二つのタイプに分けられる。このうちオペラ・ブッファは、オペラ・セリアの幕間に上演されるインテルメッツォが独立発展したもので、狂言回しともいうべきコメディア・デラルテの様式が取り入れられることが多い。ペルゴレージの「奥様女中」 はインテルメッツォの代表的な例で、本来のオペラ・セリア「誇り高き囚人」の方は初演から不評で今日では忘れられてしまった。